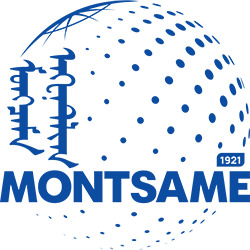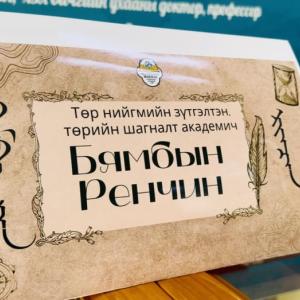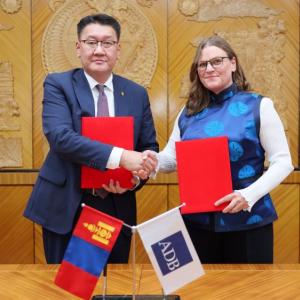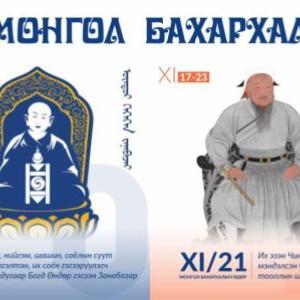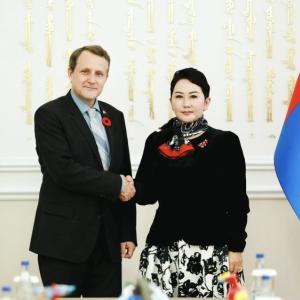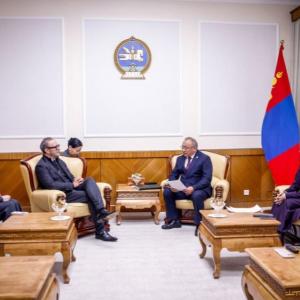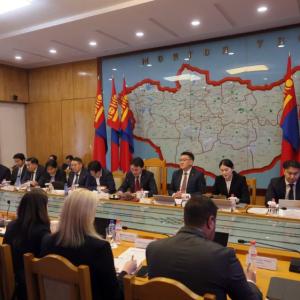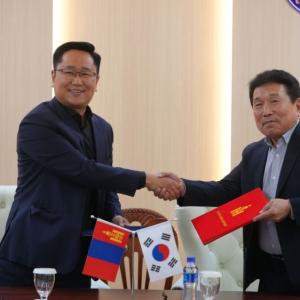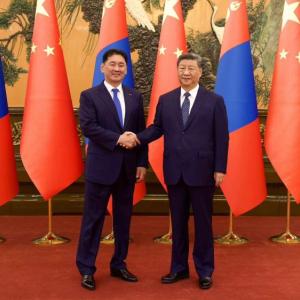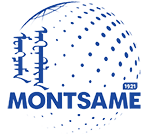バヤルトサイハン総裁:金融システム健全化と能力強化に向け構造改革実施
経済モンゴル銀行(BoM)ナドミド・バヤルトサイハン総裁に経済情勢や今後のチャレンジ等について聞いた。
――国家統計委員会が、昨年度について経済成長が加速し、伸び率が6.9%に達した、4年ぶりの好調と発表しました。景気回復に対するモンゴル銀行の貢献について教えてください。
経済信用の回復を図り、他方で金融における仲立ち機能を担い、経済成長の基盤づくりへ貢献したと言える。年末にかけて好調な景気で、国内総生産の伸び率も、当初の予測を上回った。しかも、インフレ率も8%で、BoMが目指す適切水準並みである。
貴行は2016年と17年、マクロ経済の安定化、経済危機克服のために全力を傾注した。また、経済対策と各国際機関の支援、協力が効果を発揮した。一方、2018年度は回復基調が続いた年となった。商業活動の活性化や経済拡張には、期待感のほか、具体的な出資がなくてはならない。昨年度における融資の伸びが20%超え、銀行部門が1月当たりおよそ2兆トゥグルグを供給するなど、BoMの通貨政策や銀行部門の構想改革で具体的な成果が表れた。融資に係るパフォーマンスも改善され、貸出約定平均金利の推移も1年間で3ポイント下がって16.9%となった。輸出高も史上最多の70億米㌦、海外直接投資も19億米㌦に達した。
――モンゴル経済は2015年~2017年初頭にかけて大変でした。総裁に就任してから、何を心掛けていましたか
BoMは、経済危機を克服するため、主に5つの取り組みを実施。一つは、銀行部門に関する法的環境の再整備。経済低成長から脱却するために銀行部門の抜本的な改革が必須。それは、銀行部門を規制する主な法律が10年~20年が経ったからだ。もう一つは、国際通貨基金(IMF)拡大信用供与措置における当事者である。次は、外貨準備高の増加。4番目はBoM健全化。最後は、BoMにおける人材育成だ。
――総裁着任前におよそ2%前後のインフレ率を8%までに上昇させたとの批判があります。経済が成長の軌道に乗りつつあるが、モンゴル銀行が本来の役目を果たしたと思いますか
当然ながら批判などの意見がある。ただ、根拠に基づいているかどうかだ。BoMの政策について、国際金融機関や信用格付け会社など専門家らは、別の見方を示している。低インフレ率は、モンゴルのような新興国にあるということは、むしろ低成長を意味する。経済構想、インフラ整備、気候条件、所得水準、消費衝動など、物価の基本要素から見ると、先進国ならではの2%のインフレ率維持は条件が整えられていないわけだ。2016年度の第3、第4四半期に物価下落が続き、デフレや経済縮小も表れた。家計所得が12カ月連続の減少、消極的な貸出など、銀行が緊縮を始めてからだ。一方、2018年は経済成長に伴う内需拡大が、物価上昇をもたらした。
BoMは、当然、物価上昇を詳しく分析した。今後中期においてインフレ率8%が望ましく、これを基礎に経済活性化に向けて方策を講じている。
――トゥグルグ安が進み、1米㌦が2000トゥグルグ台から2600トゥグルグまで反発しました。トゥグルグ安について、貴行総裁に責任があると言われていますが、それはどうでしょうか
モンゴル通貨トゥグルグは2016年度の第2四半期に20%下落し、最も信用を失った通貨の一つであった。2010年代から始まった財政不健全と期限が差し迫った政府債務、国際収支の不均衡、外貨準備金の減少など、国はデフォルト寸前だったが2つの教訓を得た。一つは財政健全化、債務マネジメント。もう一つは、公共事業に対する資金拠出を控えることである。現在は、外貨準備金が順調に増加し、投資家に対する信用醸成も出来ている。BoMは、急速な為替変動をもたらす住宅ローンような事業に対する資金拠出の抑制、銀行システムに対するストレス・テスト実施、中央銀行の独立性を引き上げを行った。
――外貨準備金は約35億米㌦に達したが、2018年、米ドルに対してトゥグルグは8.9%下落しました。その訳は?
以前に比べると、外貨準備金面で物価及び金融安定化に対するリスクを緩和することができる。2018年、米国連邦準備制度の金融引き締めが世界的に外貨の国外流出を招き、各国でドル高と自国通貨安をもたらした。また、米中貿易摩擦も追い風となり、ドル高を長引きさせた。
国内為替市場が2018年上半期、相対的に安定していたが、第2四半期はドル高へ圧力がかかった。原因は、経済回復に伴う外貨需要の拡大である。輸入は2016年の約35億米㌦に対して2018年に約60億米㌦に増加した。また、サービスの輸入も拡大した。国もチンギス債やティム・サム債の債務返済を履行。その反面、輸出向け輸送低下、政治的な不確実性などに牽引されて為替市場も揺れた。しかし、それ以外の原因がみつからなかった。
BoMは、昨年、およそ12億米㌦の為替介入を実施。最も変動が激しかった11月、12月に約4億8500万米㌦の投入が出来た。これはこの2年間の成果ともいえる。また、今後も急激な為替レート変動が生じないことに対する証しである。我々は、2016年のことを2度と味わないように、2020年からの債務返済に向けてしっかり準備しておくべきである。
――堅調維持と高成長率であるが、実感がないとして問題視されますが、どうしたらその実感が湧きますか
国民は、経済低迷期と違って、成長加速期にその効果を学校やインフラなど公共施設に対する出資を通じて間接的に受益している。どれぐらいの人が、所得増額などで経済成長の加速を実感しているかは重要なポイント。それを推定するため、どのぐらい資産を生産したか、どうやって生産したか、この2つである。前者は実質的な経済成長。後者は、経済分野の中で、どの分野が一番成長したかを見る。モンゴルの場合、鉱業などの分野が高成長だった。だから、成長安定は大事。従って、経済が継続的な拡張を続けると、多くの国民がその受益者となる。
――世界経済動向について、「チャレンジ」、「リスク」、「不透明性」などキーポイントがよく聞かれますが、BoMは、これをどう見ていますか
2019年度は経済堅調が維持されると見ている。輸出収入と海外直接投資、銀行貸出、公共投資などから見ると、堅調が続くだろう。もちろん、いろいろ課題はあるが、国内消費、投資、輸出も好調と予測。2019年に関して言うと、対リスク備えの年になる。我々はこの2年間、債務危機、為替危機、銀行部門危機といった3つの危機に瀕したが、今は成長軌道に乗っている。
世界経済が不透明感にさらされている中で、BoMのやることは確実であり、金融システム健全化と能力強化に向けた構造改革を引き続き実施する。通貨政策として通貨維持、インフレ圧力のない成長を図る。中央銀行による政策決定の透明性確立に向けて、意思決定の根拠となる分析力の強化、当事者間の協調を図る。
 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar