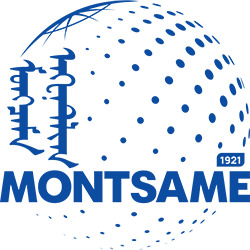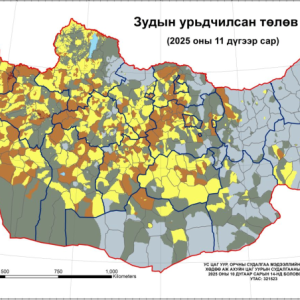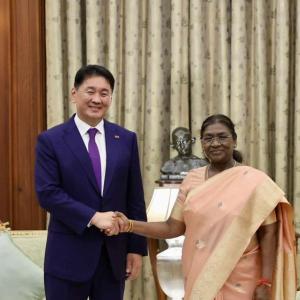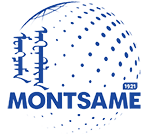2017年は、モンゴルにとって挑戦の年 ! ( 2 )
経済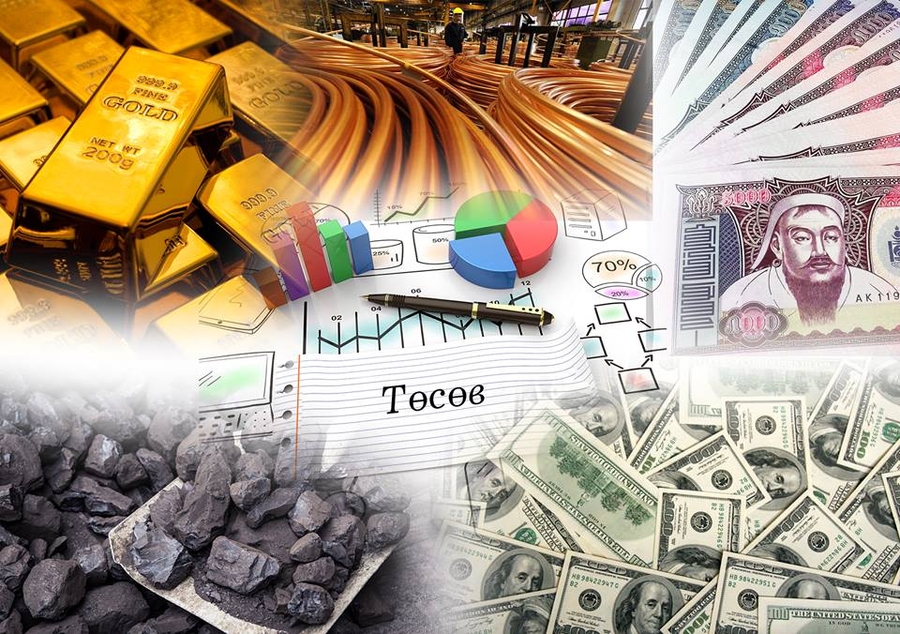
2017年度、為替市場動向について
2016年の為替市場は、一時的に1米㌦が2700トゥグルグ台まで下がるなど、急激なトゥグルグ安に見舞われた。このトゥグルグ安は、国内産業基盤が軟弱な上、過剰に輸入消費に依存するモンゴル経済に対する大きな打撃であった。専門家らは、この現象について「一時的な急上昇に過ぎない」との見解を示したが、去る2016年で世界の最も価値が下がっている通貨の一つがモンゴル通貨のトゥグルグとなった。これに対して、モンゴル銀行は政策金利の引締め措置を取った結果、トゥグルグ安には歯止めがかかり、徐々に安定感を取り戻しつつある。
しかし、2017年は対米㌦為替レートがどうなるかが気になるところだ。経済学者らは、主力輸出品である石炭や銅の世界相場価格が為替レートにおける変動に大きくかかわるとしている。国内商業銀行らは、2017年度の経済動向に関する報告書でも、経済成長率が1.3%で、対米㌦トゥグルグの為替レートが2500トゥグルグ前後だとの予想値をまとめている。世界銀行(WB)は、モンゴル経済の外部要素によるリスクが高く、外貨準備高が不十分であるため、モンゴル銀行が依然として金融政策を維持、継続させるべきだとの見解である。また、モンゴル銀行が政府のプロジェクト融資を貨幣発行で補うべきではないとした。さらに、変動相場制の維持で、外貨準備高の保全と外部要素に対して市場メカニズムによる調整をすすめた。
しかし、2017年は対米㌦為替レートがどうなるかが気になるところだ。経済学者らは、主力輸出品である石炭や銅の世界相場価格が為替レートにおける変動に大きくかかわるとしている。国内商業銀行らは、2017年度の経済動向に関する報告書でも、経済成長率が1.3%で、対米㌦トゥグルグの為替レートが2500トゥグルグ前後だとの予想値をまとめている。世界銀行(WB)は、モンゴル経済の外部要素によるリスクが高く、外貨準備高が不十分であるため、モンゴル銀行が依然として金融政策を維持、継続させるべきだとの見解である。また、モンゴル銀行が政府のプロジェクト融資を貨幣発行で補うべきではないとした。さらに、変動相場制の維持で、外貨準備高の保全と外部要素に対して市場メカニズムによる調整をすすめた。
経済学者の中から、「国が外国投資の誘致と外貨準備高の増加を図る中で、国外への資本流出を取り戻すための政策が必要だ」とする者も現れている。彼らは「国外に流出した資本がおよそ20~40億米㌦だと推計されるが、全額を取り戻せば国内のドル建ての貯金利息も下がる」などと経済における良い影響がたくさんあると訴えている。
鉱物資源基金は、不況の中で重要な役割を果たす
モンゴルは、鉱物資源の埋蔵量で世界トップ10位に入るほど地下資源が最も豊富な国の一つである。鉱業関連で、モンゴルは2011年に海外投資が史上最高額に達した。しかし、こうした絶頂はすでに過ぎ去ってしまった。経済学者らは、こうしたモンゴルの現状について「政府は、鉱物資源の売上金の一部を財源とする鉱物基金などの将来に向けた開発より、むしろばら撒きの方に走ってしまった。その結果が今のモンゴルだ」と指摘する。
外貨準備高が8000億米㌦を有7日、シャンギリ・ラ・ホテルで、在モンゴル米国商工会議所が「トップ民間企業の経営者らが語るモンゴル経済情勢と2017年の動向」という討論会を開いた。この会には、「エム・シー・エス(MCS)グループ」のJ.オド会長、石油関連の「ペトロビス社」のJ.オユンゲレル社長、「ワグナー・アジア」社のスティーブ・ポッター代表取締役、国際金融公社の在モンゴル代表のトウェン・グエン氏らがパネリストとして招かれたほか、100社の代表が参加した。パネリストらは、モンゴル経済の今後の動向や農牧業、鉱産業、メガ・プロジェクトなどについて率直に話し合った。一方、参加者の関心が経済の多角化や法規の一貫性や継続性、国際通貨基金(IMF)との拡大信用供与措置に対して高かった。
エム・シー・エスのJ.オド会長は「2 0 1 7年は、経済多角化を図って、最適の政策決定で地域の開放性のある快適的な投資先としての環境を整えることで実質的な経済振興と雇用創出につながる年である」と述べた。
ペトロビス社のJ.オユンゲレル社長は「国は輸出総量増加、その中での農産物の比重を上げるべき。さらに民間企業に対する法規の一貫性を図らなければならない。モンゴルの企業発展につながる最新の技術革新などを導入できる投資家らも必要だ」とした。ワグナー・アジアのスティーブ・ポッター代表取締役は、モンゴルの発展可能性に触れて、他国との比較研究の重要性を指摘。また、海外投資及び国内投資の意欲につながる企業成長を奨励する長期的な一貫性のある政策は、発展の良い材料ともなるとした。
国際金融公社の在モンゴル代表のトウェン・グエン氏は、IMFの拡大信用供与措置について「財政健全化は、民間企業の成長と投資家の信用に繋がる」と語った。一方、在モンゴル米国商工会議所のジェイムズ・リオッタ会長は、民間の連携強化と事業活動に対する最適な環境づくり、外国人投資の誘致、モンゴルにおける法的環境の一貫性を図るために、同会議所が設立されたとしてその意義を強調し、今後も活動を活発化させるとしてその意気込みを語った。
在モンゴル米国商工会議所、討論会開催「トップ民間企業の経営者らが語るモンゴル経済 情勢と2017年の動向」するノルウェー政府も原油収入を資金源とした国富年金ファンドを運営し、経済支援政策をうまく講じている。このファンドは、運営資金が実際の原油収入よりも多いことが指摘されている。専門家も経済不況時には、こうした基金が重要な役割を果たしていることを指摘。モンゴルでも、鉱物資源税を資金源とする人
間開発基金があったが、蓄積された資金をばらまいてしまったのも事実であり、大勢の専門家から批判の的となった。
主力輸出品の石炭や銅の価格と好況の兆候
酉年は、2012~15年の間に続いた地下資源の価格下落にようやく歯止めがかかる兆候が見られている。つまり、市場における石炭や銅、石油価格が以前の高値に回復する要素がみられるという。専門家らも、価格上昇が維持されれば、モンゴル経済にとって好影響だとしている。
モンゴルの経済は、その鉱物資源の依存度が高いことは言うまでもない。ドナルド・トランプ新米国大統領が打ち出したインフラ開発向け1兆米㌦融資が実現されると、その連鎖効果として国際市場における鉱物資源価格の上昇が期待される。一方で、中国の過去30年間に維持し続けた2桁の経済成長率が2010年代から減速している。2016年度は、その成長率が6.7%となった。今後も中国経済が景気減速を続ける傾向であるが、中国政府としては,景気加速を図るはずだ。去る2016年、中国は8000万人を貧困から救済している。まして中国本土における工場や生産力が十分であるため、海外に向けて工場建設を勢力的に取り組んでいる。市場エキスパートらは、アメリカや中国の開発政策を鉱物資源の価格上昇の材料となると結論付けている。
経済学者Ch.オトゴチョロー氏は、「石炭分野は、世界の動向を見極める必要がある。というのは、世界は石炭の使用をなるべく控えようとしているからだ。中国も大気汚染問題や公害問題で多くの炭鉱を閉鎖に追い込んでいるのも事実だ。諸国際機関も2017年にみられるの石炭価格上昇が維持し難いとの報告をまとめている。中国経済の景気減速に関連して2018年から石炭価格が再び下落する可能性が十分ある」と石炭の価格上昇に
関して懸念を述べた。
モンゴルもこうした石炭価格の上昇を受けて、経済における比重が大きな炭鉱を稼働させて、活用する必要もある。一方、銅の価格に関して、今の価格の継続が濃厚である、との予想がある。2019年から再び回復する可能性があるというが、1㌧当たり5000米㌦前後で安定する見通しだ。だから専門家らは、モンゴルの銅産業に関して、競争力底上げにつながる無駄な費用を削減し、それを高水準で維持すべきと指摘する。そのほか、外貨獲得の重要な手段の一つが金である。2016年は金採掘量として2011年の最高量までに届かなかったもの
の、充分な収益となった。金の価格も1オンス当たりが1400米㌦前後だという。
モンゴルは、自らの能力を充分に発揮できたら、世界市場における鉱物資源の価格上昇が助けとなって、不況脱却も考えられる。即ち、好況の兆候ということだ。
本誌 B.アリオンザヤ記者
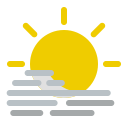 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar