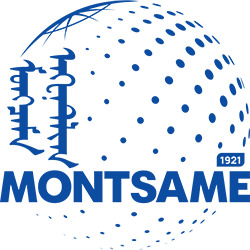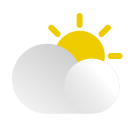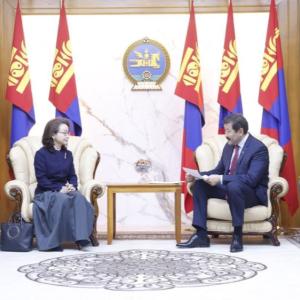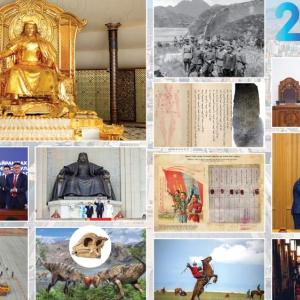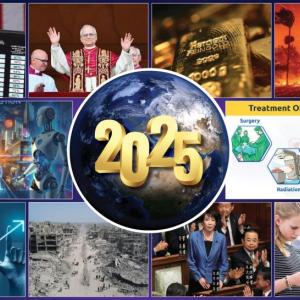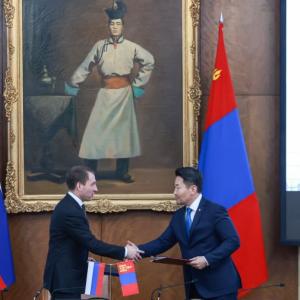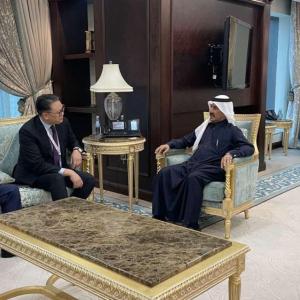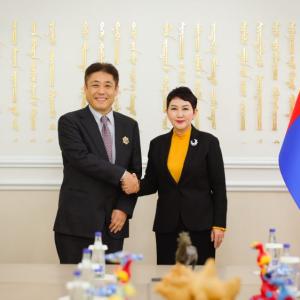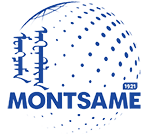インタビュー

(ウランバートル市、2025年12月4日、国営モンツァメ通信社)国際医療福祉大学卒のモンゴル人初の理学療法士バトチメグ・テムーレンさんに、日本で留学経験、貴重な思い出、これからの志について話を伺った。
――自己紹介のほどお願いします。
バトチメグ・テムーレンと申します。小学校3年生から卒業まで、日本に住んでいた。来日した理由は、母が博士号を取得するためである。
――第一言語は日本語ですね。
そうである。小学校一年生をモンゴルで終える前に、来日したため、モンゴル語は話せるが読み書きできないのが問題になっていた。
――日本へ留学したきっかけは何でしょうか。
日本語ができるし、日本に馴染みがある。自分の本当にやりたいことを見つけて、将来の仕事に直結する勉強をしたかったからである。
――なぜ、理学療法士を選んだのですか。
千葉県の国際医療福祉大学を卒業し理学療法士になった。理学療法士というのは、リハビリ専門職種である。理学療法士の中でモンゴル人でおそらくはじめてである。小さい頃からバスケやバレーなどスポーツが大好きで、高校の時に「スポーツと医療、両方に関われる仕事はないか」と考えた時に理学療法士を知った。当時のモンゴルではほとんど知られていない職業だったため、「これを勉強して母国に持ち帰りたい」と思ったのがきっかけである。
――日本留学で得たものは何でしょうか。
一番みについたモノは、患者さんとの接し方である。理学療法士という職業の特徴として働いているときに、患者さんと結構近い。そのときに、皆さんとどうやって接していくか。たぶん、モンゴルにはまだ進化していない患者さんと接し方、道徳についてよく学んだ。具体的には、絶対、患者さんの目線の下にいること。目線より上であれば態度の大きくなってしまう。
――モンゴルで働いてみていかがですか。
最初に感じたのは、やはり、リハビリというものがあまり馴染みがなかった。そんな中でどうやって人々にリハビリに関する理解を広めようか問題であった。
――この3年間を振り返るとどう感じますか。
一番最初の頃より、運動へ抵抗がなくなっているように感じる。その原因として一番の理由は、モンゴルの年齢層が低く若い人たち多い。その若者は運動に興味があったり、普段からやっているので、その影響もあるかと思う。
――留学中に行き詰った経験はりますか。
大学1年の解剖学などの専門用語が本当に厳しかった。子ども時代に住んでいたとはいえ、医療の日本語は別次元である。とにかく毎日覚えるしかなく、必死で乗り越えた。
――次世代へのアドバイスをお願いします。
一番目、けっして頭がよかったわけでない。それでもできたのは、毎日ちょっとでも勉強することは大事である。たとえ、一日だけでも休もうとしたらだめである。ちょっとだけのことでも毎日やる。二つ目は、自分の好きなことをやる。自分がやりたい職業、将来も続くなので、好きなことを追求する。
――心に残っている貴重な思いで何でしょうか。
大学の先生である。自分がその大学発初のモンゴル人留学生であった。勉強も生活も人生相談もすべて受けて止めていただいた。あの先生がいなければ今の自分はない。

――日本人とモンゴル人の違いについて教えてください。
モンゴル人は好き嫌いがはっきりしている。この点は違うと思う。
――日本人と上手く接するコツありますか。
相手が言いたいことをしっかりと考えるべきある。例えば、日本人は日常的に人といい接し方をしないといけないということを小さい頃から身についている。そのため、本当に言いたいことを言えない人もいたり、言いたくないことを言ってしまう人もいたりするので、本当に言いたいことを聞くのが大事であると思う。
――これからの志についてお願いします。
職業である理学療法士もリハビルもモンゴルでより広めていきたい。今働いている職場で、短下肢装具というものをひろめていきたい。モンゴルにはまだなかったので、日本とは少しやり方は違うが、その人の足をスキャンして3D上で出して、その足の形にあわせるようにこのデザインを出している。
――日本の皆様へ一言をお願いします。
日本は幼少期と大学時代、2度にわたり日本にお世話になった。特に「人との接し方」、「謙虚さ」、「相手を思いやる心」は、日本と日本人から学んだ最大の財産である。本当にありがたいと思っている。これからもモンゴルと日本の架け橋になれよう頑張る。
――ありがとうございました。

(ウランバートル市、2025年11月27日、国営モンツァメ通信社)モンゴル、そして世界史に名を刻んだ偉大なチンギス・ハーンの名を冠した国立博物館を巡る旅を紹介したい。今回、同テーマを取り上げるのは、3年前の2022年に、モンゴル史に黄金の文字で刻まれる大規模なプロジェクトを、モンゴル国民自らの力で実現させたためである。その結実が、ほかにもない「チンギス・ハーン国立博物館」の建設である。それでは、この特別な博物館についてより深く知るため、サンピルドンドブ・チョローン館長兼モンゴル科学技術功労者兼歴史学者に話を伺った。
ーー世界に、歴代の帝国の指導者をテーマにした有名な博物館が数多く存在します。その中で、チンギス・ハーン国立博物館は、どのような点で特に際立っているのでしょうか。また、チンギス・ハーンの歴史的影響力を、他の帝国の指導者らと比較すると、どのような興味深い結論が導き出せると考えられますか。
「チンギス・ハーン」国立博物館の設立は、6年前、オフナー・フレルスフ大統領が当時首相を務めていた際に決定された。この決定は、チンギス・ハーンの名声を世界に広め、啓蒙の殿堂を設けるという歴史的な一歩でもあった。
世界に、名を轟かせ、歴史に足跡を残した王や貴族は数多く存在する。しかし、チンギス・ハーンのように、人類に大きな影響を与えた王はごくわずかである。特に過去1000年間で、際立った偉人の一人であると言えるでしょう。
人類の王国国家が最も活発であった時代から、すでに2000年の歳月が流れた。そのうちの1000年間、偉大なチンギス・ハーンの名声のもとに語り継がれてきた。
偉大な王や貴族の博物館は、大きく分けて二種類ある。一つは、偉大な王や貴族自身がかつて居住していた宮殿を博物館として公開したもので、もう一つは、王や貴族の遺物や記念品を収蔵し、その功績をたたえるために設立された博物館である。
チンギス・ハーンの名を冠したこの博物館は、モンゴル帝国の歴史を伝える博物館にあたる。その展示内容は、大きく三つに分かれている。
第一に、チンギス・ハーンとその祖先である匈奴時代の歴史。第二に、チンギス・ハーンの子孫とモンゴル帝国の時代の歴史。第三に、20世紀初頭、チンギス・ハーンの血を引く人々によって築かれた歴史である。
私たちは70年間、チンギス・ハーンの足跡について語ることが制限されていた。1962年にチンギス・ハーン生誕800周年を祝った際、多くの人々が不当な扱いを受けただけでなく、チンギス・ハーンの歴史を特別に語ることや偉大なハーンを敬う権利も認められていなかった。ところが、1996年に「ワシントン・ポスト」はチンギス・ハーンを「Man of the Millennium(千年の人)」と称賛した。
そのため、チンギス・ハーンの故国を訪れる誰もが、チンギス・ハーンの歴史を学びたいという願望や知ることの必要性を感じることであろう。その歴史を学ぶ上で最も重要なのは、チンギス・ハーンが生まれ育った聖地と文化遺産である。この博物館は、モンゴル国政府が自らの資金で建設した。モンゴルの学者らの理念と知識を土台に、モンゴルの建築家や技術者の知恵、国内外の支援者の協力、そしてモンゴルの芸術家らの知見と創造力を結集して築かれた。
また、世界的なパンデミックという困難な状況の中で完成したこの博物館は、過去30年間におけるモンゴルの文化分野で最大規模の事業のひとつとなった。

天皇陛下が2025年7月7日、「チンギス・ハーン国立博物館」をご訪問された際のご様子
――モンゴル帝国は当時、世界人口のどれほどを支配していたのでしょうか。また、それは世界史上どれほど特別な出来事だったのでしょうか。
人類はモンゴルの歴史、とくにチンギス・ハーンの歴史を様々な視点で見てきた。一方はチンギス・ハーンに征服された側の視点があるし、他方はモンゴル側から「我らがチンギス・ハーン」として見る視点もある。
しかし近年は、人類全体、特に世界の優れた研究者らの学術的成果によって、チンギス・ハーンの歴史を捉える視点が変わってきた。チンギス・ハーンは単なる征服者ではなく、ユーラシアに大規模な交流を生み出した人物として見られるようになっている。当時存在していたのはユーラシア大陸だけで、アメリカ大陸やオーストラリア大陸はまだ「発見」されておらず、アフリカにも強大な帝国はなかった。従って、チンギス・ハーンの帝国の成立により、ヨーロッパとアジアの間に大規模な交流が生まれ、特に経済・産業面での活発な往来が実現した。さらに、最大の交易路であったシルクロードが安全に保たれるようになったことも大きな功績である。数世紀にわたって対立の原因となってきた宗教に対し、自由な信仰を認めた。かつてアジアとヨーロッパの人々は、お互いを遠く隔たった存在だと思っていた。しかし、チンギス・ハーンの時代に、大陸間のつながりや文化的影響が生まれた。このように、チンギス・ハーンは人類の歴史において、数多くの驚くべき業績を残した人物である。今日の人類がなお解決できず、実現を夢見ている多くの課題は、13世紀のモンゴル帝国によってすでに克服されていた。そのため、ジャック・ウェザーフォードは著書『Genghis Khan and the Making of the Modern World』の中で、チンギス・ハーンを現代世界の形成に大きく寄与した人物として描いている。
現代の私たちは、戦争の問題や経済の自由化、宗教の自由といった多くの課題を十分に解決できていない。しかし、モンゴルの偉大なハーンは、13世紀にこれらの課題をすでに解決していた。
このような歴史的事実を踏まえ、チンギス・ハーンやモンゴルの歴史に対する世界の見方も少しずつ変わりつつある。そして、この博物館は、そのような新しい視点や理念を広めるための重要な存在として設立されたのである。
インタビューの続きは「モンゴル通信」新聞でご覧ください。


モンゴルの偉大なダシドルジ・ナツァグドルジ作家の誕生日である11月17日に、岡田和行東京外国語大学名誉教授兼モンゴル文学研究者が『アルタン・ハラーツァイ』モンゴル文学研究・分析書によりナツァグドルジ記念賞を受賞した。その翌日、岡田氏はモンゴル国立大学で学生や研究者を対象に、モンゴル現代文学をテーマとした講演会を行い、インタビューに応じた。
ーーナツァグドルジ記念賞の受賞、誠におめでとうございます。以前、「もしモンゴルに来ていなかったら、日本でサラリーマンになっていた」とお話しをされましたが、長年モンゴルで過ごされた経験は、先生の人生や研究にどのような影響を与えましたか。
モンゴルに来る前は、正直なところ、モンゴルを専門に研究しようという意識はあまりありませんでした。留学は2年間でしたが、最初は生活が大変で、早く帰りたいと思うこともありました。しかし、学生寮でモンゴル人学生と同室になり、授業を受けるうちに次第に興味が湧いてきました。食事や寒さで生活は楽ではありませんでしたが、現地の人々と関係が深まるにつれ、様々なことに関心が生まれました。あの留学経験が、現在の研究者としての道、そしてモンゴル現代文学を専門にする選択に大きな影響を与えました。
ーーモンゴル文学や思想をご研究されている外国人研究者として、日本と比べた場合、モンゴル文化のどの点が特に際立っており、またどの点に共通性を感じられますか。
文学作品、特に小説を読むと、日本とは大きく異なる点が多々あります。例えば生活様式は大きく異なりますし、現在のウランバートルの都市生活には東京と変わらない部分もありますが、地方の遊牧民の暮らしを描いた作品には、細やかな描写が多く登場します。そのため、理解が難しい場面もあります。
しかし、人を愛する、憎むといった人間の基本的な感情が共通しており、その普遍的な部分が非常に理解しやすいのです。環境や風俗が違っても、人間の内面は共有できます。
文学というよりも、日常生活で戸惑ったことの方が多かったですね。例えばモンゴルでは、後ろから足を踏まれたときに、なぜか握手をする習慣があります。最初はまったく意味が分かりませんでした。こうした日常の文化的差異には驚かされることが多かったです。
インタビューの続きは「モンゴル通信」新聞でお読みください。




(ウランバートル市、2025年11月10日、国営モンツァメ通信社)
毎年10月29日に恒例で開催される「ビエルゲー・ナイト」は、モンゴルの伝統と 現代の活気が調和する温かみあふれるイベントである。今年も8歳~80歳までの 幅広い世代が集い、会場はデール姿の参加者たちの笑顔と熱気で活気に包まれて いた。遊牧民の暮らしや精神を体現する伝統舞踊「ビエルゲー」が、人々をつな ぎ、モンゴル人としての誇りを呼び覚ますのである。今回は、ビエルゲー文化の 魅力を国内外に広める活動を行っている「オグトルグイン・ビエルゲー」教育セ ンターの創設者であるSh.ノミンエルデネ氏に話を伺った。
ーービエルゲーとどのよ うに関わりましたか。
私は本職がバレエダンサーで、その後、振付も 学んだ。「オグトルグイ ン・ビエルゲー」という 教育センターを設立し て、今年で7年目を迎え る。私の舞踊の基礎はモ ンゴル舞踊で、両親が幼 いころから学ばせてくれ た。専門はクラシックバレエであったが、モンゴル舞踊の意味を学ぶほ ど、自分の文化に強く惹 かれるようになった。人間には生まれてきた使命や 創造の課題があると思う が、私にとってそれがビ エルゲーなのかもしれない。
ーービエルゲーは他の舞 踊とどう違いますか。
ビエルゲーは単なる動き ではない。モンゴル人の 身体、魂、意識の統合を 表す舞踊である。ビエル ゲーをすることで、ヨガ やフィットネス、瞑想を したかのような心身への 効果が得られる。例えば ヨガは呼吸が重要である が、ビエルゲーは動きそ のものが自然に 呼吸を整え、 正しいリズム へ導いてくれ る。身体の骨や筋肉 をバランスよく使い、 内なるエネルギーや精 神面にも作用する。現 代社会で、生活や仕事の 影響で体が緊張しやすい が、ビエルゲーはそれを 鎮め、心身の中心を保つことを教えてくれる。 基本姿勢である「ヤゾ ゴール姿勢」は大地と つながり、芯を象徴す る。

ーー「オグトルグイン・ ビエルゲー」を設立した 目的は何ですか。
主な目的は伝統文化の 復興である。例えばモ ンゴル人は「ジョー ライ・ゲルデン」と いう歌を聞くと心が 高揚するが、体をど のように動かせばよ いか分からないこと がある。私たちはその 感覚をビエルゲーを通 して表現し、復活させ る。教育プログラムは 連続的に行われ、基礎 を教えれば、受講者自身 が自然に美しく舞えるようになる。
ーー初回の「ビエルゲ ー・ナイト」はどのよう に開催されましたか。
最初は約50人が来てくれたらいいなと思ってい たが、実際には約10人が来た。「私」と「ビエルゲ ー」を大切に思う人々の ために公演を行ったこと が、今も鮮明に思い出される。当時は毎月のイベ ントとして開催してい た。今年は7周年を記念し てフェスティバル形式で 開催し、約400人が集まった。これは私たちの長年の努力の成果である。
インタビューの続きは「モンゴル通信」新聞でご覧ください。





(ウランバートル市、2025年10月16日、国営モンツァメ通信社)DataReportalが発表した2025年の調査によると、モンゴルではおよそ260万人がソーシャルメディアを利用しており、これは全人口の約74.4%にあたるという。数字の上からも、ソーシャルメディアがいかに人々の日常生活に深く浸透しているかがうかがえる。
情報収集や交流、自己表現の手段として欠かせない存在となった一方で、ソーシャルメディアの過度な利用が心の健康に影響を及ぼすケースも少なくない。
こうした現状を踏まえ、今回はモンゴル国立大学心理学科長であり、博士・教授のムンフナサン・デレゲルジャブ氏に、ソーシャルメディア利用とメンタルヘルスの関係について話を伺った。
ーーソーシャルメディアや情報の流れは、私たちや社会の心理にどのような影響を与えているのでしょうか。
現在、マスメディアは社会心理に大きな影響を及ぼす主要な手段となっている。モンゴルで以前はテレビがその中心的存在であったが、今はソーシャルメディアがその役割を担うようになった。FacebookやInstagram、などのSNSは、時間や場所を問わず、短時間で情報を見たり共有したりできるため、テレビやラジオ、新聞といった従来型メディアよりもはるかに強い訴求力を持っている。
現代において、ソーシャルメディアが社会全体の心理に影響を与え、時には“世論”そのものを左右するほどの力を持つと言っても過言ではない。
ーー近年、「情報過多疲労症」という言葉が聞かれるようになった。情報社会に生きる私たちは、どのように心の健康を守るべきなのでしょうか。
現代の人々は、自ら望まなくても絶えず情報の波にさらされている。興味のない内容であっても、次々と流れてくるニュースや投稿を目にし、つい読んでしまう。脳は視覚や聴覚を通じて入ってくるあらゆる情報を処理しようとするが、その量が膨大なため、知らず知らずのうちに疲弊してしまう。
さらに、SNS上のインフルエンサーの発信や広告は、無意識のうちに私たちの思考や選択に影響を与える。自分の意思とは関係なく多様な情報を受け入れ続けることは、ストレスや不安、精神的な疲労の原因になりかねない。
こうした状況の中で心を守るには、“情報との距離の取り方”を意識することが重要である。情報に触れる時間をあらかじめ区切り、本当に必要な情報だけを選んで取り入れる――こうした習慣が、心の健康を保つ第一歩になるでしょう。
ーーネガティブなニュースや情報に触れたとき、個人としてどのように向き合い、どんな行動を取るべきなのでしょうか。
これは非常に難しい課題である。私たちは見たくないと思っていても、有料広告や“トロール”と呼ばれる偽アカウントなどが拡散する情報を、避けることなく目にしてしまう。こうした膨大な情報を、個人が選別もフィルターもかけずに受け入れてしまうこと自体が、問題の根本にあると言えるでしょう。そのため、まず必要なのは“デジタル・リテラシー”を身につけることである。
たとえば、新しい製品を使うときに「どう使うのか」と取扱説明書を読むように、テクノロジー時代を生きる私たちも、“デジタル社会の中でどう行動すべきか”という基本を理解する必要がある。
また、自分のSNSアカウントに投稿する内容については、「自分の発言は世界中の人に見られている」という意識を持つことが大切である。たとえ個人のページであっても、その言葉一つひとつが誰かを傷つけたり、誤解を生んだりする可能性がある。だからこそ、投稿する前に一度立ち止まり、冷静に見直す習慣を持ってほしいと思う。
さらに、SNS上で“積極的に発信しない”という選択肢もある。なぜ、コメント欄で怒りや不満をぶつける必要があるのでしょうか。もしSNS上での罵倒や感情的な書き込みによって社会問題が解決するのなら、それも意味があるかもしれない。しかし現実には、社会は政策や制度、実務的なプロセスを通して着実に動いている。だからこそ、私たち一人ひとりがデジタル空間における自分の立ち振る舞いを見つめ直し、冷静で成熟したオンライン行動を学ぶことが求められているのである。


(ウランバートル市、2025年9月19日、国営モンツァメ通信社)サマンサ・モスティン・オーストラリア総督はモンゴル訪問の一環、記者会見を開催した。
31年前にビル・ヘイデン元オーストラリア総督がモンゴルを訪問して以来、私が2人目の訪問者となった。1990年代に両国関係が構築・強化され、深い絆を持つようになった。オーストラリアはモンゴルの第三隣国であることを誇りに思っている。同国賓訪問の際、両国の協力関係が新段階に格上げされた。両国は教育分野をはじめとする様々な分野で強固な関係を築いており、特にオーストラリアの大学・高等教育機関の卒業生による活動を通じて、ますます発展している。1990年代から始まった奨学金プログラムにより、6000人の学生がオーストラリアで教育を受けている。また、数万人のモンゴル人がオーストラリアで学び、働いている。同訪問の際に「オユトルゴイ」プロジェクトを視察した。リオ・ティント社とモンゴル政府が推進中の同プロジェクトにオーストラリアの数百社のエンジニアリング会社やコンサルティング会社が関わっている。同プロジェクトを通じてモンゴルの未来を担う若者たちが知識と技能を身につけている様子を見るのは本当に喜ばしいことであった。二国関係の様々な側面を私に示してくださったモンゴル国大統領に心より感謝を申し上げる。

ーー今回のモンゴル訪問は、政治的にも経済的にも二国関係を一段と引き上げる意義深いものになったと考えています。モンゴルにとって、鉱業以外にもインフラや開発分野への投資が非常に重要であると見ていますが、この点についてオーストラリアの投資家らはどのように考えていますか。
まず申し上げておきたいのは、私は個人としていかなる投資や金銭面での利益関係も持っていないということである。過去30年間、モンゴルの投資環境を整えるために尽力してきた。例えば、リオ・ティント社がモンゴルに投資し、事業を実施したことは非常に成果のある取り組みとなった。要するに、企業は重要な事業を実施してきた。両国が民主的な価値観を共有し、法の支配を尊重し、法律を遵守していれば、投資にとって信頼できる安定した環境が整うと考える。
ーーご訪問中に、オーストラリアが実施している事業を実際にご覧になりました。モンゴルで進行中のプロジェクトの成果や実施状況をどのように評価していますか。
二国が友好的で親密な関係にあれば、間違いなくパートナーシップに繋がると実感した。パートナーシップから良い成果が生まれる。その成果を最も明確に示している実例は技能向上である。オーストラリア人がモンゴル人にスキルを身につけさせ、育成してきたため、モンゴルの若者らは世界各国で働けるようになった。このような成果に対し投資家らは大きな誇りを感じている。投資は単にビジネス分野にとどまらず、教育や市民社会、ジェンダー平等、所得面で取り残された人々への支援など様々な形で行われる。大統領も英語教育の向上を特に強調した。従って、オーストラリアは今後も教育分野での協力関係を発展させ、特に英語教員の派遣や支援に注力する。
ーー近年、モンゴルでジェンダー平等や女性の意思決定の場での参加拡大に向けた取り組みが進められています。高い地位にある女性としてこの点についてどのようにお考えでしょうか。
今回の訪問を通じて、モンゴルが女性の経済的権限の向上と自立支援に特別な関心を寄せていることを認識した。例えば、「オユトルゴイ」プロジェクトの全従業員の25%が女性である。これはモンゴルだけでなく、世界に向けても非常に重要なメッセージとなっている。なぜなら、鉱業分野で女性が働くことは決して簡単なことではない。また、ゲル地区を訪れ、女性の気候変動への適応能力を向上させる取り組みも見た。母親であり地域のリーダーでもある方が気候変動に対応するため太陽光パネルを設置し、クリーン・エネルギーを活用しているのを目の当たりにして、とても感動した。これらの事例をオーストラリアで紹介したいと考えている。
ーー「オユトルゴイ」のようなプロジェクトを通じてモンゴル・オーストラリア関係を更に発展させることは可能でしょうか。
政治的な立場からコメントできない。二国間パートナーシップの発展について両政府が協議して決定すべき。 しかし、「オユトルゴイ」プロジェクトを視察する際、投資を呼び込む必要があること、両国とも民主主義国家であるため、基本理念が共通していることを実感した。民主的な価値観を有し、安定した投資環境が整っている国への投資は素晴らしい機会であると考えている。モンゴルで事業を展開している企業代表者らは、鉱物資源分野の発展により、モンゴルの国内総生産に貢献するだけでなく、世界の富創出にも寄与していると考えていることを表明した。つまり、鉱業分野は今後も重要な分野であり続けるであろう。新事業に関して両国のビジネス関係者が決定するであろう。二国間の投資は広範囲にわたり、深い意味を持っている。モンゴル人はオーストラリア人に学び、またオーストラリア人もモンゴル人に学んでいる。これも投資の一つの形である。


(ウランバートル市、2025年8月11日、国営モンツァメ通信社)オフナー・フレルスフ大統領の後援のもと、「世界女性起業家フォーラム」がモンゴルで今月25日と26日に開催される。
このフォーラムは大統領が女性を支援した大規模の4回目の事業で「Inspire-Impact-Invest」とスローガンのもと、世界25ヵ国の216人の女性起業家が集結する。同フォーラムを迎え、大統領の事業・プログラム調整、市民社会政策顧問から話を伺った。
--オフナー・フレルスフ大統領はジェンダー平等の保障、女性関与、リーダーシップの拡大に注力しています。これに関する大統領が提唱した主な事業、法的環境改善からお話をはじめましょうか。
―モンゴルは偉大な歴史、特殊な遊牧文化の価値観を誇る国民である。我々は母を尊敬し、女性を大事に愛し、言葉、教え、行動を敬意してきた。これは正しい伝統だけではなく、現代でも社会の価値観、政策の基礎思想のままである。モンゴルは女性権利を非常に昔から保障し、どんな政権のもとで、尊重してきた。我が国は、ジェンダー平等確保に関して、地域の諸国に比較すると着実な進歩、豊富な経験の積んでいる。それを共有する成果が大いにある。モンゴル国は1924年に制定された最初の憲法では、男女平等の権利を認め、女性に、選挙権を付与した。これは、アジアで初かつ歴史的な出来事である。我々は、歴史的な100周年を昨年お祝いし、女性権利保障を目的とした初の非政府組織である「モンゴル女性組合」の周年を迎えた。我が国は歴史的な成果を誇るべきではあるが、政治における女性関与は十分な基準に達していないのは調査結果を見られる。大統領の提唱で上程した「政党に関する法」改正案、「国家大会議の選挙に関する法」改正案は昨年、可決された。したがって、直近の8回の国会選挙によって選出された608人の議員のうち、女性は60人(全体の10%)にとどまっていた。しかし、2024年の総選挙で32人の女性議員が選出され、全体の25%を占めるまで増加した。これにより、アジア地域で国会における女性参画を主導する国となった。また、上記の法律では、2028年以降、政党は立候補者の少なくとも4割りを同一の性別で構成することが義務づけられている。この基準が達成されれば、2030年に「持続可能な開発(SDGs)目標5」つまりジェンダー平等保障は完全に実現される。


(ウランバートル市、2025年8月6日、国営モンツァメ通信社)世界の舞台でバレエ芸術を広めているモンゴル人バレエダンサー、エ.アーンダーさんが夏休みの帰国中にインタビューを伺った。
米国・コロラド州で生まれ育った同氏は、5歳のときにバレエを習い始めて以来、一貫して努力を重ねてきた。国際的なコンクールでも優れた成績を収め、海外のバレエ団からも高く評価されている、数少ないモンゴル人バレエダンサーの一人である。現在はドイツ・ザールラント州にあるクラシック芸術劇場でプロのバレエダンサーとして活躍している。
―― クラシックバレエの世界に足を踏み入れたきっかけは何だったのでしょうか? また、ここまでの成功において、ご家族の支えが大きかったのではないでしょうか。
5歳のときにバレエを始めた。それ以前は、歌や絵画、ゴルフ、水泳など、いろいろなことに興味を持っていたが、中でも体の動きで感情を表現できるバレエに強く惹かれた。最初の先生はロシア人で、厳しい中にも多くのことを学んだ。その後、ワールド・ダンス・スクール、コロラド・クラシック・バレエ、デンバー芸術学校で基礎を学び、更にサンフランシスコ・バレエ・スクールに進学した。2021年に同校を卒業し、シカゴの『ジョフリー・バレエ』で2年間研修を受けた後、現在はプロとして舞台に立っている。
最初は、バレエがこんなにも厳しく、また多くの費用がかかる世界だとは知らなかった。例えばトウシューズは、一日使っただけで履けなくなってしまうこともあり、1足で100㌦もする。そんな中、両親は私のために懸命に働き、高収入の仕事を目指して努力してくれていた。その姿を見て、私自身も決して諦めずに努力し続けようと決意した。私のすべての成功の背後には、家族の深い愛情と支えがある。
両親は1998年にモンゴルから米国に移住し、私を愛情いっぱいに育ててくれた。両親はいつも私のそばにいて、どんなときも応援してくれた。その支えがあったからこそ、今の私がある。私の家族は社会活動にも積極的で、その姿勢は今も変わっていない。
ーーバレエダンサーとして舞台に立つうえで、美しさや才能、均整のとれた体型が求められるとよく言われます。あなたが選んだバレエという職業の、最も大きな特徴は何だと思いますか。
バレエは“音のない演劇”だと思っている。言葉を使わずに、体の動き、表情、ジェスチャーで感情やストーリーを表現する。
一方で、コンテンポラリーダンスは、私にとってもっと自由な表現ができる場でもある。一方、クラシックバレエには、舞台に立った瞬間に自分の持てるすべてを注ぎ込まなければならないという、張り詰めた緊張感がある。一度ミスをしてしまえば、やり直しはできない。
だからこそ、自分を限界まで追い込むこと、より高みを目指そうとする気持ち、それがとても美しいと感じる。バレエには“到達点”というものがなく、生涯をかけて学び続ける芸術である。どんなに優れたソリストでも、成長の余地があり続ける。だから私は、バレエこそ“学びの美しさ”を体現している芸術だと思っている。
私自身、これまで学んできたことを次の世代に伝えたい、バレエを愛する若者たちに少しでも刺激を与えたいという想いがある。いつか自分なりの形で、モンゴルのバレエや舞台芸術の発展に貢献できたら嬉しい。
私は海外で生まれ育ったが、モンゴル人であることをいつも誇りに思う。初めて自分で振付けたモンゴル舞踊では、民族文化の要素を取り入れたところ、外国人の観客からとても高い評価をいただいた。それが自信にもなり、創作の幅が広がっていった。
モンゴルに帰国する前には、『The HU』の音楽とモンゴル舞踊のリズムを融合させたコンテンポラリー作品を振付けた。舞台の背景には、モンゴルの雄大な自然を映し出したが、それがとても好評で、観客の方々から『モンゴルに行ってみたい!』という声をいただいたのがとても印象的であった。
ーーバレエダンサーの方々は、人生の大半を舞台の上で過ごされると思いますが、リハーサルの合間やオフの日はどのように過ごされていますか。
私は普段のほとんどの時間をバレエに捧げているが、それ以外にも写真を撮ったり、旅行したり、登山やヨガを楽しんだりと、たくさんの趣味がある。
バレエという芸術は、60%が頭脳と精神、残りの40%が身体の動きでできていると感じている。そのため、脳を休ませる時間を大切にしており、自然の中に身を置き、山や川を眺めるのが好き。私が住んでいた米国・コロラド州には、標高4200㍍以上の山が58座ある。全米でも70座に満たないこの高峰のうち、私はこれまでに12座を登った。それは私の誇りでもある。
今回、久しぶりにモンゴルに戻ってきて、自然の美しさからたくさんのエネルギーをもらっている。


モンゴルの政治、宗教、文化芸術の偉大な功労者であるウンドル・ゲゲーン・ザナバザルの生誕390周年が本年にあたる。モンゴルの偉大な啓蒙思想家であり、初代ボグドの歴史的功績、芸術的才能、そして遺した文化遺産について、ザナバザル美術館の館長であるP.バイガルマー芸術学博士に話を伺った。
ーーモンゴルが誇る稀代の偉人、ウンドル・ゲゲーン・ザナバザル(「徳の高い活仏」の意)の生誕390周年が本年にあたります。偉大なる人物の名を冠したこの美術館には、どのような素晴らしい作品が所蔵されているのでしょうか。
ウンドル・ゲゲーン・ザナバザルによって確立された様式や、その御手による作品は、美術館の展示品の中で最も価値の高いものとして評価されている。モンゴル美術の偉大な代表者であるウンドル・ゲゲーンの手になる多数の作品が、当館には所蔵されている。
その中には、「白ターラー」、五仏(五智如来)、「菩提ストゥーパ」、「マイトレーヤ」、「柔和なる音声」、および「ハンドジャムツ母像」などのオリジナル作品が含まれている。
また、粘土像、鋳造仏、タンカ(仏画)、アップリケ、木版画など、様々な技法を用いて表現された様式に基づき、ウンドル・ゲゲーンの後の弟子たちによってウンドル・ゲゲーンの姿や仏像も、美術館の貴重な展示品の一部である。更に、ウンドル・ゲゲーンの美術制作された作品群も当館に保存されている。

ーーパリの「ルーヴル美術館」でウンドル・ゲゲーンの作品が展示された際、現地紙は「偉大なるザナバザル」と評したといいます。これは、レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ、世界的な巨匠たちと肩を並べるほどの偉大な才能を持っていたことを示すものです。 ウンドル・ゲゲーン・ザナバザルの唯一無二の芸術的魅力は、どこにあるのでしょうか。
ザナバザルの作品の創作技術の素晴らしさについては、多くのことを語ることができる。1993年にフランスでモンゴルの優れた展示品を集めた展覧会が開催された。この展覧会には、ウンドル・ゲゲーンの「グリーンターラー」像が展示された。その際、フランスのメディアで大きな話題となり、美術評論家や研究者たちから高い評価が寄せられた。

「グリーンターラー」「金剛ターラー」「白ターラー」は、モンゴル美術のみならず、世界の仏教美術においても他に類を見ない傑作と高く評価されている。パリのルーヴル美術館で展示されて以来、国際的な専門家らがこれらを「アジアのマドンナ」と称えた。
これにより、ウンドル・ゲゲーンの作品は、モンゴル国内にとどまらず、アジア、東洋、さらには世界の芸術を代表する傑作の一つであることが明らかになった。さらに、ルネサンス期のレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロといった偉大な巨匠たちの作品にも匹敵するほど、極めて高い芸術的完成度を備えた素晴らしい作品であることが示されている。
人間の身体の比率や寸法に関する特別な教えは、「ダンジョール(仏陀の大乗経典で、基礎理論を網羅した百科事典のような書物)」にも記されている。例えば、古代インドの仏像制作における基準寸法を示した『プラティマラクシャナ』や『チトララクシャナ』といった大乗仏教経典が存在する。ウンドル・ゲゲーンは、これらの経典に基づき、「ダシャタラ」や手のひら10枚分の長さといった基準を用いて作品を制作していた。
このように、ウンドル・ゲゲーン・ザナバザルがモンゴルのみならず東洋美術全体における古典的巨匠であることは明らかである。同氏は、インド、チベット、ネパールにおける仏像造形の厳格な形式や伝統を独自の発想で打ち破り、モンゴル民族の美的感覚や人々の生活習慣、願いを巧みに取り入れて表現した。
その結果、ウンドル・ゲゲーンは、当時として前例のないモンゴル独自の仏像造形流派を築き上げるとともに、彫刻芸術におけるブロンズ鋳造技術の基礎を確立した人物として正当に評価されている。
ーーウンドル・ゲゲーン・ザナバザルの作品には、どのような卓越した技法が見られるのでしょうか。
ザナバザルの作品は、人間の体の美しさや形態、手の動き、所作、表情、衣装、装飾品に至るまで、細部を一切妥協せず、緻密な寸法と比率に基づいて制作されている。「グリーンターラー」「ホワイトターラー」「五本尊」「金剛ターラー」などの作品は、世界的にも希少な古典彫刻の最高峰と高く評価されている。
また、ウンドル・ゲゲーンの彫刻は、単なる外見の表現にとどまらず、仏像に込められた深い意味や思想、感情までも巧みに表現している。そのため、見る者に深い信仰心を呼び起こし、仏教哲学を芸術を通じて伝える力を備えている。
作品はまるで命が宿り、動きや感情を持っているかのように感じられるため、モンゴルの人々はウンドル・ゲゲーンを「転生した芸術家(生まれ変わりの名匠)」と称えている。
また、ウンドル・ゲゲーンは、仏教美術において独自の表現スタイルを確立した人物でもある。現在、世界中の研究者らが同氏の作品や芸術思想を研究しており、ウンドル・ゲゲーンが制作した仏像や美術品は、各国のオークションにおいて高額で取引されている。


(ウランバートル市、2025年7月5日、国営モンツァメ通信社)オフナー・フレルスフ大統領の招請により、日本の徳仁天皇と雅子皇后両陛下がモンゴルを国賓として訪問する。これに関連し、モンゴル国立大学科学学部アジア学科教授であり、「JUGAMO」協会会長でもあるS.バトトルガ氏に、日本国と日本人について話を伺った。
ーー日本はアジア諸国の中で、ノーベル賞受賞者の数でトップに立ちます。なぜ日本人は他の国の人々と違うのでしょうか。
今日は日本について話せることを大変嬉しく思う。私は日本研究者として30年間ぐらい働いた。もちろん、日本と日本人について全てを知っているわけではないが、研究を重ねるたびに興味深く、ますます惹きつけられることに驚かされる。まず最初に、日本の地理的な位置を強調したい。日本は海に囲まれ、豊かな天然資源に恵まれていない島国でありながら、約1億2000万人が暮らしている。これだけ多くの人が島国で調和を保ちつつ、高度な発展を遂げたことが大変興味深く、注目すべき点である。また、日本人は歴史の中で数多くの試練に立ち向かい、それを克服してきた。例えば、第二次世界大戦に参戦し、国土で核爆弾の投下を受け、甚大な被害を被った。更に、現代の重大な課題に最初に立ち向かい、その解決に尽力している。そのため、この国の経験が極めて重要であると考える。加えて、欧州文明を学びながらも、自らの独自性を持つ現代国家を創り上げた歴史も非常に興味深いものである。
ーー世界を驚かせるような事例もあります。例えば、福岡市で道路が陥没し巨大な穴が発生した際、わずか48時間で完全に修復したことです。カタール及びロシアで開催されたサッカー・ワールド・カップを観戦した日本の応援団がスタジアムを清掃してから退場しました。では、日本を発展させる上で日本人のどのような資質が最も重要な役割を果たしたのでしょうか。
外部から見て、日本人は非常に規律を重んじ、倫理観が高く、互いに敬意を払う国民であると感嘆される。そのように見えるのも、日本が農耕文化があるため、人々が協力して田を耕し、米を育て、収穫するという共同体的な仕組みが伝統として存在しているからであると考えられる。日本の村落共同体で培われた協調精神や集団意識を尊重する価値観は、現在の日本社会でも高く評価され、重視されている。言い換えれば、他者への敬意、自己への敬意を重んじることは、日本文化において非常に重要な価値観とされている。要するに、公共の利益を第一に考え、自己の利益を後回しにするという独自の文化的特徴がある。
日本人は自分を強調したり、目立たせたりすることを控える。このような姿勢は、過度に控えめで、分かりづらく、窮屈であると見なされることもあるが、決して短所ではない。むしろ、集団で暮らす現代社会において極めて適応的であり、優れた長所であると評価できる。従って、現代日本の高度な発展の背景に国民のこのような気質や価値観が大きな強みとして作用したのではないかと考えられる。加えて、日本人が物事に対する忠誠心や誠実な姿勢は、非常に特徴的であり、高く評価される。日本人の特徴は、自らの役割や業務に対して全力を注ぎ、最善を尽くし、最後まで責任を持ってやり抜くことである。日本の政治家は、不適切な行為があった場合に謝罪し、責任を認めて職を辞することが多く見受けられる。日本人にとって名誉とは、自分一人のものではなく、所属する組織、家族の名誉も含む広い概念である。家族の名誉や家系の名誉を保持し、敬うことと密接に関連する。
ーーモンゴルと日本は「平和と繁栄のための特別な戦略的パートナーシップ」の関係にあります。この関係を発展させるために何が重要であると考えますか。また、日本人に接する際に注意すべき点は何ですか。
非常に重要な課題である。現在、モンゴルと日本の政治関係は過去最高の水準に達している。とはいえ、日本の価値観をより深く理解することが重要である。モンゴル側は、特定の分野や課題、方向性において優先順位をつけ、より積極的に探求・研究する必要がある。より具体的な分野において、実効性のある積極的な連携を図るべき。私は日本人の文化的・精神的特性について言及する際に、誠実さや原則を重んじる姿勢、そして同意したことに対して責任を持ち、名誉を守る文化を強調した。チンギスハーンによってモンゴル帝国が構築された時代のモンゴル民族は、高い倫理観を有し、社会が合理的に構成されていたと推察される。これは、『元朝秘史(モンゴル秘史)』にも明確に記されている。友情への忠誠、名誉を尊ぶ精神、民への真心からの慈しみという数々の価値観が我が祖先に根付いていた。歴史の中で喪失された価値観を日本の模範から学ぶことが可能であると考えている。近年、日本は世界情勢の変化に対応して、自国の歴史を振り返ることを議論している。第二次世界大戦前にどのような経験をしたのか。その後に構築した社会は正しかったのか、間違っていたのか。何を失ったのかについて話し合っている。
ーーモンゴルを訪れた日本人は、多くの素晴らしいことを書き残しています。「モンゴルの大地で私は人間の本質を再発見しました。ここで、人間と自然は切り離せない一つの存在です」と日本の有名な作家が記しています。日本人はモンゴルのどのような点により興味を持ちますか。
まるで「私たちは誰か」という問いをしているかのように聞こえる。モンゴル人は歴史の中で多様な姿を持ちながらも、「モンゴル人はこうあるべき」という様々なイメージを想像し、そのような人物を作り上げようとしてきたと思う。日本人は1900年~1920年にかけてモンゴルを訪れ、調査を行った。島に住む日本人はモンゴルで何を感じたのであろうか。多くの地域を調査した司馬遼太郎という人物は、モンゴルで多数のことを見出したに違いない。日本人はモンゴル帝国の歴史を非常に詳しく研究し、ボグド研究を高いレベルで発展させた。この国は、自らの強さを保ち、多数の重大な危機を乗り越えるために、強靭かつ賢明で、人間の本質を保持している国々の歴史を研究する。そのような国々の中にモンゴルも含まれる。日本の天皇陛下が即位後、初のモンゴル訪問をされることは、モ日関係を重視していることの表れである。
ーーモンゴル出身の力士たちは、モ日関係に多大な貢献をしたと言えるでしょう。モンゴル出身の力士が相撲界に足を踏み入れてから33年間で6人のモンゴル人横綱が誕生しました。日本人は同件についてどのような感想を持っているのでしょうか。
モンゴルは古代からブフという伝統格闘技を受け継いできた国であり、日本の相撲も独自の伝統を有している。たとえ同じく格闘技であっても、モンゴル相撲と日本の相撲は、それぞれ独自の形式、作法、文化的な特色を備えている。なぜ日本はモンゴル人力士を相撲に受け入れてきたのかと考えることがある。モンゴル人が力強いため、横綱が誕生することを予想していたのであろう。予想していたにもかかわらず、なぜ多数のモンゴル人力士を相撲界に受け入れたのか。それは外来の文化を柔軟に受け入れる能力の表れでもある。必要な物事や自己の再生・強化に資する条件を柔軟に受け入れつつも、独自の個性や伝統を守り続ける技術を培ってきた国である。米国の戦略家と地政学者は「日本人は外見上、教養ある文化人であり、いくつかの分野において戦略的な能力を発揮していることを証明した」と評価している。従って、モンゴル人力士を相撲土俵に迎え入れる際に、将来を見据えたと考えられる。外国出身の力士は相撲土俵で横綱に昇進する際に、日本の伝統を最高度に敬うことが強く求められる。「あなたは日本の一部となった。このことを常に自覚してください」と言われてきたと推察される。モンゴル出身の横綱はこの教えを忠実に守り続けている。
ーーモンゴル人力士が相撲土俵に上がったことで、どのような進歩や影響をもたらしたと日本人は考えているのでしょうか。何を語り、何を強調していますか。
日本人は自国の伝統や文化を大切にしており、その代表的な例の一つが、相撲という伝統文化である。一見すると単なる格闘技のように見えるが、力士の生活様式や上下関係の礼儀作法、相撲ならではの規律や伝統を受け継いできた文化である。モンゴル出身の横綱たちは自らを高いレベルで鍛え、数々の厳しい試練を乗り越えた末に地位を築き上げたのである。彼らが相撲界で収めた成功は、モ日関係の発展に大きく貢献し、非常に重要な役割を果たしてきた。加えて、モンゴルを世界に広く知らしめる上でも極めて重要な役割を果たした。相撲を敬愛する人々は、次第にモンゴル人力士にも深い敬意を抱くようになり、更にモンゴル相撲にも興味を持ち、観戦するようになった。従って、モンゴル人は新たな可能性を切り拓き、その過程で日本の方々から多大な支持を受けたと言っても過言ではない。相撲のような数多くの機会が次々と訪れることも十分に考えられる。モンゴル人の我々は信頼に応え、最善のレベルで二国関係を発展させるために努力すべき。
ーー「JUGAMO」協会は設立30周年を迎えています。日本帰国留学生の会は、モ日の友好と協力の懸け橋となることを目指しています。日本と日本人をモンゴル人に紹介する他、モンゴル人向けにどのような活動を行っていますか。
私は、日本帰国留学生によって構成される「JUGAMO」協会の会長を務めている。今年、設立30周年という節目の年を迎える。「JUGAMO」は日本留学中のモンゴル人、留学経験者、日本での生活経験を持つ全ての人々を繋ぐ、自由でオープンな交流団体である。過去30年間で、多くの実績を積み重ねてきた。とりわけ、モンゴルと日本の友好の懸け橋としての使命を立派に果たしてきた。日本で津波と震災が発生した際、私たちは一早く支援を呼びかけ、募金を通じて心からの連帯と共感を示した。更に、日本人をモンゴルへ呼びかけるための環境整備やビジネス分野での連携に関する情報交換を行い、来モした日本人を暖かく歓迎し、安全かつ快適に過ごせるよう対応する。その結果、日本大使館やJICA、モンゴル在住の日本人が同協会の理念を深く理解し、協力して事業を実施するようになった。日本に関連する人々の交流を促進し、紹介や情報提供を行うとともに、日本文化や日本人の本質を学び、自身の再発見に寄与する多様な活動を企画・運営している。この節目にあたり、過去30年間「JUGAMO」を代表し支えてきた全ての先輩方および若手の皆様に心よりお祝い申し上げる。




(ウランバートル市、2025年7月4日、国営モンツァメ通信社)井川原賢在モンゴル日本国特命全権大使にモンゴルと日本の協力関係について話を伺った。
ーーモンゴル人はかねてより日本に興味を持っていました。大使は両国関係がいつから始まったとお考えですか。両国関係の発展の歴史の中で、どの時期が特にターニングポイントだったと思いますか。
モンゴルの方々が日本に興味を持ち、親近感をいだいてくださっていることを嬉しく思います。私たち日本人もモンゴルに対し、同じように親近感をいだいています。さて、日本とモンゴルの関係の歴史は、研究者によると遙か悠久の昔からあったそうですが、その関係を大きく変えたのは、間違いなく1990年、モンゴル民主化の年だったと言えます。今年はモンゴルが民主主義体制に移行して35周年ですが、言い換えれば、日本とモンゴルが民主主義、人権、法の支配といった共通の価値観の下で、35年間共に歩んできたことを意味します。
ーー日本政府の開発援助(ODA)により、JICA等がモンゴルのインフラ、医療、教育などの分野でさまざまなプロジェクトを実施しました。これらの中で最も具体的な成果を上げたものはどれだと考えますか。
日本政府によるモンゴルに対するODAは1977年に締結された経済協力協定に基づき実施された無償資金協力「ゴビ・カシミヤ工場建設」に始まりますが、1989年度までは研修員の受入、専門家派遣、機材供与を中心とした技術協力および文化無償資金協力といった限られた分野に留まっていました。モンゴルが社会主義体制から市場経済体制に移行した1990年以降、一般無償資金協力による積極的支援が始まるとともに、円借款が初めて供与され、日本の対モンゴルODAはさまざまな分野で本格化します。モンゴルの民主化への移行期という最も苦しい時期に日本の支援は極めて大きな役割を果たすとともに、現在に至るまで一貫してモンゴルの国造りを担う人材育成を行ってきており、2024年度までの累計支援総額は3,700億円(25.6億米ドル相当)に達しています。
どの支援も時宜にかなったものであり、高い成果を上げていますが、特に私が取り上げて申し上げたいのは、円借款の下で建設されたチンギスハーン国際空港です。
2008年E/N署名、2013年着工、2020年完工、2021年開港と、長い年月をかけて実現した656.57億円の大型プロジェクトでした。モンゴルの国際旅客数は1999年の約14万人から2024年には約175万人に増加していますが、チンギスハーン国際空港の完成により、空港の信頼性、安全性が向上し、「GO MONGOLIA」キャンペーンの推進による観光開発が進みました。

チンギスハーン新国際空港の初便記念式典
また航空貨物輸送量が増え、空港周辺開発も含めた経済効果も高く、モンゴルの国際化を新たな段階に引き上げることができました。さらに、今年1月、日本政府は、2017年にモンゴルのIMF拡大信用供与措置(EFF)の導入以降、例外を除き新規供与が停止されてきた対モンゴル円借款の手続きを再開する決定を発表しました。
これにより今後の需要拡大に応じるチンギスハーン国際空港の拡張をはじめとしたモンゴルの発展に重要なインフラ開発にさらに寄与することができると考えています。
ーー大使にとって、モンゴル社会に忘れがたい影響を与えた「草の根」プロジェクトの最も特別な例を共有していただけますか。
実は、モンゴルに対する「草の根・人間の安全保障無償資金協力」も1990年から開始されており、今年で35周年になります。これまで35年間で613案件(2024年度末時点)、供与総額は約4,800万米ドル(2024年度末時点)になります。草の根案件のひとつひとつは比較的小規模で、社会的に大きなインパクトはないかもしれませんが、地域住民に直接裨益する点でその地域の方たちにとっては大きな影響力があります。不衛生なトイレや寒い教室を草の根によって改修し、安心して教育や医療を受けられる環境を整備することは、日本政府が掲げる対モンゴルの国別開発協力方針の「包摂的な社会の実現」に合致しており、改修後に訪れた幼稚園や学校、病院で、先生や子どもたち、患者の方たちの笑顔を見られることは何よりも嬉しいことです。
ーーモンゴルと日本の間で締結された経済連携協定(EPA)の恩恵を両国はどのように活用していますか?対モンゴル日本投資の拡大のための新たな可能性は、どの分野にあると考えますか?
EPAは両国の経済互恵関係強化のための重要な枠組みであると考えています。日本モンゴルEPAを締結したにもかかわらず、貿易インバランスが縮小していないといった声を、時折聞きます。EPAは貿易や関税を自由化することで、直ちに貿易インバランスを解消させることを目的とするものではなく、投資や知的財産権保護、電子商取引、また、投資環境といった、通商分野の幅広い協力関係を促進することも含まれています。
EPAの枠組みを通じて、貿易のみならず、このような分野も含めた、経済関係を拡大させることを議論し、互恵関係を促進していくことが両国にとって重要と考えます。
昨年11月には、ウランバートルにおいて、日本とモンゴルの貿易・投資の拡大や協力関係の強化等について協議する「日本・モンゴル官民合同協議会」が開催されました。両国の経済協力を協議するセッションでは、デジタル、ヘルスケア、スタートアップ、ビジネス環境整備、日モンゴルEPAの利活用推進など、今後の協力の可能性について、日本モンゴル双方から事例も交えて議論が交わされ、これらの分野での今後の協力強化を目指しています。 加えて、現在、経済・開発省やモンゴル商工会議所との間で、日本の地方の経済団体とモンゴルの経済団体の交流を強化していくことについても、意見交換を行っています。また、今年は4月から10月までの間、「大阪・関西万博」が開催されています。万博を通じて、多くの日本人にモンゴルのことを、もっと知ってもらい、親しみを持ってもらうことを通じて、経済交流がより、拡大し深まることを願っています。
ーー両国の関係には一般市民の相互理解が非常に重要です。これは両国の関係をより明示的かつ明るく豊かなものにします。大使個人として感謝している、思い出深い日本人とモンゴル人との関係の例をお話しいただけますか。
日本人とモンゴル人の感動的な「人」対「人」の交流の話をよく聞きます。ご存じの方も多いと思いますが、日本の有名な作家、故司馬遼太郎さんとウランバートルホテルで働いていた通訳者の故ツェベグマーさんとの交流は多くの日本人を感動させました。1973年に紀行文執筆のためにモンゴルを訪れた司馬さんは、日本語通訳者のツェベグマーさんと出会いますが、そのときは両国の体制の違いから彼女の人生について詳しい話を聞くことはできませんでした。1990年に再度モンゴルを訪れた司馬さんはツェベグマーさんを取材し、「草原の記」を執筆します。彼女の人生には多くの苦しみがありましたが、しなやかに強く生きたモンゴル人女性の生き様に私たちは深い感銘を受けました。現在も、ひとり娘のイミナさんとバータルツォグトさんご夫妻は私たち家族のよき友人であり、ツェベグマーさんの遺志を継ぎ、日本とモンゴルの交流のために尽力してくださっていることに感謝が尽きません。

またチンゲルテイ区のノゴーンノール公園ではウルジートグトフさんという一般市民の方が、ご自身が利用許可を得た土地が、日本人抑留者がウランバートルの都市建設のために石を切り出した場所であることを知り、その歴史を語り継ぐ資料館を開設しています。もともと日本と何の関係もなく、歴史の専門家でもない一般のモンゴルの方が、両国関係の知られざる歴史を調べ、多くの方に伝えていこうという熱意に頭が下がる思いです。この公園は今、夏はボート、冬はスケートを地元の方々が楽しむ以外に、外国からの旅行者が訪れ、日本人抑留者とウランバートル市の歴史を知ることができる場ともなっています。 このような一般市民の交流が日本とモンゴルの関係をこれまでも、今も、これからも固くつないでいくことは確実です。
ーー日本で教育を受けたモンゴルの若者たちは、両国の架け橋としてどのように活躍していると評価しますか。
1976年に初めてモンゴルからの国費留学生が日本に留学してからまもなく50年になります。その間、日本の政府奨学金でモンゴルから約2,000 人が留学していますし、さらに私費留学も合わせると日本留学経験のある方は増えています。日本留学を終えてモンゴルに帰国した留学生の会(JUGAMO)の会員だけでも2,000人を超えています。
国費留学生や私費留学生はその後も連綿と続いてきており、その一人一人の貢献がモンゴル社会に根ざし、両国関係の促進に多大な影響を及ぼしてきています。その流れは継承されながらも、新たにモンゴルの人材育成の観点から日本政府として二つのプログラムを実施していることを紹介したいと思います。
ひとつはM-JEED(工学系高等教育人材育成支援)です。
モンゴルでは「1,000人の技術者」プロジェクトとして知られている2014年に開始した円借款事業です。この事業に基づきこれまで約1,098 人が日本に赴き、1,058 人がすでに学業、研究を終えて帰国しています。これは「点」ではなく、モンゴル経済全体の牽引ひいては産業多角化の実現という広域な「面」を対象とする人材育成を念頭においたもので、現在、今後の協力のあり方に関し議論を重ねているところです。もう一つは、2001年に始まったJDSという若手行政官育成プログラムです。これはモンゴルの行政能力を向上させるために、学生ではなく、モンゴルの中央や地方の行政組織に携わっている人たちに留学機会を与えるものであり、若手行政官としての知見に基づき日本の諸分野での成功例や失敗例を見ながら、大学で学ぶものです。モンゴルからはこれまで約430 人が参加し、すでに384人が帰国されそれぞれの行政機関や中央銀行等で活躍しております。このように拡充した制度を確実に継続しながら、流れの幅を広げていくことで、多くのモンゴルの人材が世界を舞台にモンゴルの発展のために活躍できるようになることを願っています。

ーー大使はモンゴルに初めて来てから27年過ぎました。また1991年に日本総理大臣の初のモンゴル訪問の準備に関わっていたと聞いています。それ以降、モンゴルで起こったどのような変化が興味深いと感じられますか。
モンゴルは豊かな伝統文化を継承しながらも、国際的にダイナミックに発展している点が大変興味深いと感じています。外国で学ぶことや働くことに躊躇せず飛び込む行動力があり、複数の外国語を操り、持ち前の明るさと力強さで世界のどこででも活躍されています。しかし常に母国のことを忘れず、何年か後に外国で得た知識や経験を持ち帰り、母国の発展のために役立てる方が多いと思います。今、日本で学んだり働いたりした人たちが、モンゴルの発展に寄与している姿はとてもまぶしく、希望を感じさせます。
私が1991年に西側諸国首脳の初めてのモンゴル訪問となった海部総理の訪問準備に関わった際には、新しい両国関係の創出を模索していました。
モンゴルは民主化直後のさまざまな問題に直面していましたが、私たちは常にモンゴルに対する敬意を持ち、日本としてどうやって貢献できるのか一生懸命考えていたことを覚えています。今はそのときに比べると、積み重ねてきた信頼関係が確固たるものとなっており、あらゆる分野で日本とモンゴルが手を携えてきたこと、パートナーとして歩んできた歴史が底流にあることに安心感を覚えています。
ーー日本の天皇皇后両陛下が麗しい夏の季節に美しいモンゴルを訪問する予定です。これは両国関係をどのような新たなレベルに至らしめるとお考えですか。
天皇皇后両陛下の御訪問は、日本とモンゴルの二国間関係を記す歴史書に、金の文字で記されるべき意義深い出来事です。まず、ナーダムも開催される7月のすばらしい時期に御訪問いただけるということは、モンゴルの方たちにとって大変誇らしいことだと思います。モンゴルの方たちが最高のモンゴルを天皇皇后両陛下に見ていただきたいと敬愛を持って歓迎していただけることが、私にとっても大変嬉しいことです。
次に、天皇皇后両陛下がモンゴルの方々の熱意に応えてくださったということは、両陛下がモンゴルをいかに大切に思ってくださっているかの現れではないかと考えています。
実は両陛下は即位されて7年になりますが、国際親善のための外国御訪問されたのは2023年のインドネシア、2024年の英国に続き、モンゴルは3か国目の栄誉となります。今回の御訪問は、これまでさまざまな交流により培われてきた日本とモンゴル両国の関係の新しいページが開かれるきっかけになります。両陛下の御訪問を前に、私たちの世代が先達たちから受け継いだ日本とモンゴルの信頼関係に基づいた恩恵をそれ以上の深さ、広さにして次の若い世代に引き継いでいきたいという決意を新たにしています。
ーー両国関係の未来をどのように想像し、期待していますか。
日本とモンゴルは、平和と繁栄のための特別な戦略的パートナーです。両国が、アジアにとって、さらには世界の中で、最も平和的で、最も民主主義的で、最も豊かな文化的なものを発信できるパートナーとして共に存在し、その魅力を輝かせていく未来が私の願いです。
モンゴルは多くの国々と広く交流ができる利点があります。日本は私が思うに最も平和志向で独自の文化を持ちながら人類の平和のために貢献していこうという気持ちが強い国です。
そういった両国が今、良好な信頼関係を構築していますが、これを我々が次世代も、次々世代も、50年後も、100年後も更に充実した方向へと発展せしめて、モンゴルと日本それぞれがアジア地域で、また国際社会の中で、最も魅力的なものを発信し、国民もそれを享受している国として、またパートナーとして存在し続けていくこと、そして世界中がそれを認知して、日本とモンゴルの関係を賞賛する時がくることが私の夢です。

(ウランバートル市、2025年6月15日、国営モンツァメ通信社)「持続可能性に関する対話2025―気候変動:10億本の植林」国際会議の際、Z.バトジャルガル気候研究者に気候変動および「10億本の植林」全国運動について話を伺った。
ーー「持続可能性に関する対話2025―気候変動:10億本の植林」会議の意義をどう考えていますか。
同会議で気候変動が取り上げられている。「10億本の植林」全国運動が政府の主導の下で進められ、国民、企業、団体、そして個人までが参加している。「10億本の植林」全国運動を開始する際、温室効果ガスの吸収に重点が置かれていた。具体的に、気候変動による乾燥化は、モンゴルの植生、森林、低木、灌木、草花など全てのものに影響を及ぼしている。同運動は、気候変動の緩和、適応、特にモンゴルの経済や人々の暮らしに深刻な影響を及ぼす乾燥化への対抗が最重要である。
ーー専門家として、モンゴルにおける気候変動の進行はどれほど速いと考えていますか。
気候変動は、モンゴル国土において平均気温がどの程度上昇し、温暖化が進んだかによって示される。過去80年以上の間に降水量が7〜8%減少し、平均気温が約2.55度上昇した。これは世界の平均よりも速いと考えられている。世界の平均気温を2030年まで1.5度以下に抑える目標が設定されたが、既に1.55度上昇し、目標を超えてしまった。しかし、世界の平均とモンゴルの平均は異なる。モンゴルだけでなく、地球の寒冷な気候帯でも気温の上昇と急速な温暖化が観察されている。気候変動により、自然災害の数が増加している。モンゴルは温室効果ガスを14%削減する目標を設定している。植生を増やせば、温室効果ガスを33〜34%削減することができる。しかし、私たちの力で解決されない一つの脅威は気候変動である。その原因は大気中に放出される温室効果ガスである。モンゴルが排出する温室効果ガスの量は非常に少ないものの、一人当たりや一製品当たりの排出量は他の国よりも高い。
ーーモンゴルの土壌と気候にどの種類の樹木が適合しますか。
まず第一に、その地域に自生する在来植物を中心に植えるべきである。 ただし、どのような目的で植えるかによって大きく異なる。農地で風よけとして、道路の脇では防護壁として、都市部では装飾として植えるなど、目的によって適した木が異なる。従って、植樹は政策的に、専門家の関与の下で、いわば科学的な根拠に基づいて行うべきである。あちこちに好きな木を勝手に植えて放置することは効果がない。地方に、専門家ではないけれど自発的に木を植え、経験を積み、成果を上げている多くの人がいる。その人々の優良な経験を広め、経験を共有し、助言を受けることが最も効果的な取り組みであると思う。


― モンゴル・ポーランド外交関係樹立75周年記念日を迎えて ―
(ウランバートル市、2025年4月15日、国営モンツァメ通信社)オフナー・フレルスフ大統領は、2025年3月13日~14日にかけて、アンジェイ・ドゥダ・ポーランド共和国大統領の招請により、同国を国賓訪問した。同訪問の成果および両国の伝統的な友好関係について、ナワーンユンデン・オユンダリ在ポーランド・モンゴル国特命全権大使に話を伺った。
ーーモンゴル国大統領が12年ぶりに開催した今回の訪問の成果について、どのような点を強調しますか。
今回の訪問における最も重要な成果は、伝統的な友好関係が包括的パートナーシップに格上げされたことである。わずか数日間の訪問であったが、非常に多くの成果が得られた。合計13件の協定に署名した。
今回の訪問では、今後、包括的パートナーシップ関係を発展させる方法、経済交流の拡大、政治関係の更なる強化、国際舞台での協力など数多くの課題について意見交換が行われたことが、同訪問の大きな成果である。
ーーポーランドは、モンゴルへの輸出量において欧州連合(EU)諸国の中で首位を占めている。今回の訪問に合わせて開催された二国間ビジネス・フォーラムの成果を紹介してください。
モンゴル側から約100名のビジネスマンが出席した。 モンゴルが社会主義から市場経済に移行し始めた頃、非常に多くのモンゴル人ビジネスマンがポーランドからビジネスをスタートさせたという興味深い歴史がある。現在、モンゴルとポーランドの貿易総額は1億400万米㌦に達している。この貿易額を3~4倍、可能であれば5倍に拡大するよう、全力で取り組む意向である。もちろん、伝統的な考古学、古生物学、鉱業といった分野においても、多数の事業を実施する予定である。特に、銅の加工、製錬、精鉱において、数多くの事業を計画している。
また、農業分野でも多くの進展が見られると確信している。訪問団に、7人の大臣と10人の国会議員が参加した。7人の大臣のうち、4~5人が二国間会談を行った。例えば、農業大臣が会談を開催した。今後、ポーランドの技術、ノウハウ、知識、研究成果の導入により、モンゴルの農業分野でかなりの進展が見られると確信している。
現在、約190名のモンゴル人がポーランドに留学している。同国に滞在中の1000人以上のモンゴル人を通じて、二国の友好関係が更に強化されると確信している。ポーランドに1000人以上のモンゴル人が留学した。その人々もモンゴルとポーランドの架け橋になると確信している。



(ウランバートル市、2025年3月13日、国営モンツァメ通信社)エルデネビレグ・ハリオンボルド・モンゴル国功労選手は帰国した。ハリオンボルド選手はモンゴルのモータースポーツ界で最も優れた選手の一人である。同選手は、アラブ首長国連邦(UAE)アブダビで開催された世界ラリーレイド選手権に成功裏に出場した。現在、米国・ラスベガス市に居住し、働きながらトレーニングも行っている。ハリオンボルト選手は米国に戻る前に、インタビューに応じた。
――世界ラリー・レイド選手権(W2RC)に出場されたと聞きました。同大会についてせつめいしてください。
怪我をしてから約2年間モーターサイクルに乗らなかった。3年前から少しずつ乗り始め、コンディショニングしてきた。新たなキャリアをスタートできたことを嬉しく思う。最終的に、同選手権で14位に入賞し、別の種目でそれぞれ7位に入賞した。
―― 新たなキャリアを始めたとのことですが、次の大会の予定はありますか。
今回出場した大会は3つのシリーズで構成され、多くのことを学び、貴重な経験を積んだ。従って、残りの2つのシリーズにも出場したいと考えている。
―― 以前はモトクロスで競技をされていました。今後「ダカール・ラリー」に出場しますか。
もちろん、同じ機械を使用するので、共通点はあると思う。ただ、長距離レースなので、計画作成能力、ナビゲーションの技術を向上させる必要がある。ダカール・ラリーに出場することは完全にチーム協力が必要となるので、その面においても強化を図りたいと思う。もちろん、レースの準備も進めていく。個人的に「草原からダカールへ」プロジェクトを実施する。同プロジェクトの一環として、アスリートとしての旅を記録したドキュメンタリーを制作したいと思う。主な目的は、アスリートの忍耐力とレジリエンスを見せ、精神との向き合いが成功へ導いていくのを見せることである。一人のアスリートの背後には、どれほど多くの人々の努力と貢献が存在するか示したい。
―― モータースポーツに興味のある若者にアドバイスをお願いします。
多くの若者が電話やCメールでアドバイスを求めてくる。電話で話すことと、実際に指導することは全く異なる。従って、今年の夏、モンゴルに帰国し、若者を対象に研修を開催する予定である。

(ウランバートル市、2025年3月8日、国営モンツァメ通信社)今年は28回目の「モンゴル縦文字競書大会2024」国際コンテストが成功裏に開催された。「モンゴル縦文字競書大会2024」コンテストは、国際規模での開催が2回目となり、約1200人が作品を応募した。その中に、中国・内モンゴル自治区やロシア・ブリヤート共和国のモンゴル書道家たちの作品も含まれている。同コンテストの「美しい筆跡・書道」種目で1位を獲得したO.ガンジグール・モンゴル国立教育大学の教師ーモンゴル語・文学4年生のガンジグール氏に話を伺った。
--同コンテストに継続的に参加し、今年、順位を上げておめでとうございます。『モンゴル縦文字競書大会』コンテストへの参加は何回目ですか。
『モンゴル縦文字競書大会』コンテストに、中学校の9年生と10年生の時から参加し始めた。継続的に努力した結果、2023年と2024年に受賞できたことを嬉しく思う。
--毎年のコンテストの特徴はどのようなものですか。
モンゴル民族と世界のモンゴル書道家も参加するのが特徴である。モンゴル・カリグラフィーや縦文字を一定の範囲でグローバル化させていると思う。更に、全年齢層や異なる専門分野の人々が参加できる点も非常に魅力的である。
--モンゴル語・縦文字を学び始めたのはいつですか。また、カリグラフィーはどのように学びましたか。
私はブルガン県のフタグ・ウンドル郡で高校を卒業した。6年生の時に初めてモンゴル縦文字を勉強した。とても面白く感じ、直ぐに、全文字を覚えて読みたいと思っていた。カリグラフィーは9年生の時習った。地元で筆や墨などの書道道具があまり手に入らなかったので、それをウランバートル市から取り寄せていた。手に入れた道具は大切に使い、毎日練習することはできなかった。しかし、大学に進学してから、同じ興味を持つ友人たちと一緒に技術を向上させ、楽しく学んでいる。

--カリグラフィーを通じて得られる素晴らしいことは多いと思いますが、最も素晴らしいことは何ですか。
カリグラフィーを始めてから、大きく変わったと感じている。筆と墨を使っていると、本当に落ち着く。以前は思っていることをうまく表現できず、イライラすることもあったが、今では辛いときや気が乗らないときでも、筆を握って書くと落ち着く。更に、創造的な思考や忍耐力など、さまざまなスキルも身につけることができた。一つの作品を作るためには、何日も準備し、多くの考えを巡らせ、いろいろな方法で試行錯誤を繰り返さなければならないので、その過程が非常に学びの多いものであると感じている。

--毎年のコンテストでどれくらいの時間をかけて作品を仕上げていますか
一つの作品を作るために、2、3ヶ月前からアイデアを考え始める。あるいは、半年間考え続けていたアイデアを一週間で仕上げることもある。作品を作る方法について、常に考え続ける。今年の作品もコンテストのガイドラインが発表された後にアイデアを思いつき、2ヶ月間準備をしてから参加した。
--カリグラフィーを始めて教えてくれた先生について聞かせてください。
カリグラフィーは、ブルガン県のフタグ・ウンドル郡の学校でモンゴル語・文学の教師であるD.ムンフチメグ先生に教わった。先生は、正しい座り方、筆の使い方など、自分の知識を惜しみなく教えてくれた。先生のおかげで、しっかりとした基礎を築くことができたと思う。ムンフチメグ先生を見て、自分も先生のような良い教師になりたいと強く思っている。
--モンゴル縦文字を大切にしている人々は、他の人に伝え、影響を与えることが非常に重要であると思います。この点に関して、どのような活動をしていますか。
ありがとうございます。モンゴル国立教育大学では「ティテム」というカリグラフィー・サークルが無料で運営されている。学期毎に新しい受講生を募集し、筆の書き方、竹ペン、折り紙書道などを、自分のレベルに合わせて教えている。半年間授業を行った後、学校で展示会を開くことを目標にしている。今年も新規入会者を含め、約70人の学生がこのサークルに参加している。

--教師の職業を選んだのはなぜですか。
子どものときからクラスメートに自分が知っていることを教えるのが好きで、よくおしゃべる子であった。この性格が影響したと思う。中学に進学してからモンゴル縦文字や書道を学び、教師になりたいという夢が更に強くなったと言える。D.ムンフチメグ先生は「あなたは素晴らしい教師になるでしょう」と言われたことが、私の夢をより鮮明にしたかもしれない。
--2025年から、行政公文書にモンゴル縦文字とキリル文字の併用することになりました。同件についてモンゴル語専攻の学生としてどう考えていますか。
言語は国家の免疫のようなものである。モンゴル縦文字を日常的に使い、更に外国にも広めるべきであると思う。行政公文書が両文字で作成されることに賛成しており、これをきっかけに、より多くの人々がモンゴル縦文字を日常的に使用するようになることを期待している。
--カリグラフィーを学び、競技会に参加し、展示を開き、技術を磨き、協力して取り組む経験が積み重なってきたと思います。仲間や後輩、これから学ぼうとしている人にアドバイスをしていただけますか。
カリグラフィーをする人々をとても誇りに思っている。なぜなら、最初から正しい基礎を学ぶことが非常に重要だからである。紙をどう引くか、そこから始まる。カリグラフィーは忍耐力、根気、責任感、安定感を求める。
更に、カリグラフィーは大変時間と努力を要するので、決して諦めないでいただきたい。モンゴルの免疫の一つであるため、全ての人が是非興味を持って学んでほしいと思う。
--お忙しい中お時間をいただき、ありがとうございました。学業と仕事での更なるご成功をお祈り申し上げます。

(ウランバートル市、2025年3月7日、国営モンツァメ通信社)28回目の「モンゴル縦文字競書大会2024」国際コンテストを成功裏に開催した。同コンテストの「文書以外の作品」部門で1位を獲得した、モンゴル語と書道を尊び学びながら、また伝統文化を継承している、ウランバートル市ハンウール区第34番学校12年生B組の生徒、J.アリウンゾル氏に話を伺った。
ーー「モンゴル縦文字競書大会2024」国際コンテストの「作品」部門で1位を獲得したことをお祝い申し上げます。今回が初めての参加にもかかわらず、1位を獲得しましたね。コンテストの情報は最初にどこで得ましたか。
担任の先生が毎年同コンテストの展示会を見に行く。また、『フムーン・ビチグ』縦文字週刊紙を定期的に購読する。従って、先生がサークル生徒に参加を呼びかけ、同コンテストに参加することを決めた。
ーー同サークルはいつ設立され、どんな活動をしていますか。
サークルは1年前に設立されたモンゴル縦文字の「ゲゲーン・エグシグレンン」である。サークルの顧問はG.ダワーナサン先生で、書道や筆での書き方を教えている。そして昨年の春には、「ズーンフレー」寺院のM.エルデムビレグ先生に竹筆での書き方を教わった。現在は、E.アンフバヤル先生から筆での書道の授業を追加で受ける予定である。
ーーサークルの生徒数を教えてください。
6年生〜12年生の26人がいる。
ーー「モンゴル縦文字競書大会2024」国際コンテストの12年生の部門で竹筆で書いて参加しましたね。同作品を準備するのにどれくらいの時間がかかりましたか。
私は夏に竹筆で書けるようになった。筆での書き方はまだ習っていなかったが、選んだテーマでエッセイを書き、それを縦文字にして、文字脱字の確認は済ましていた。同作品を提出する前にM.エルデムビレグ先生からアドバイスをいただいた。そして、一晩で作品を下書きせずに書き終えた。
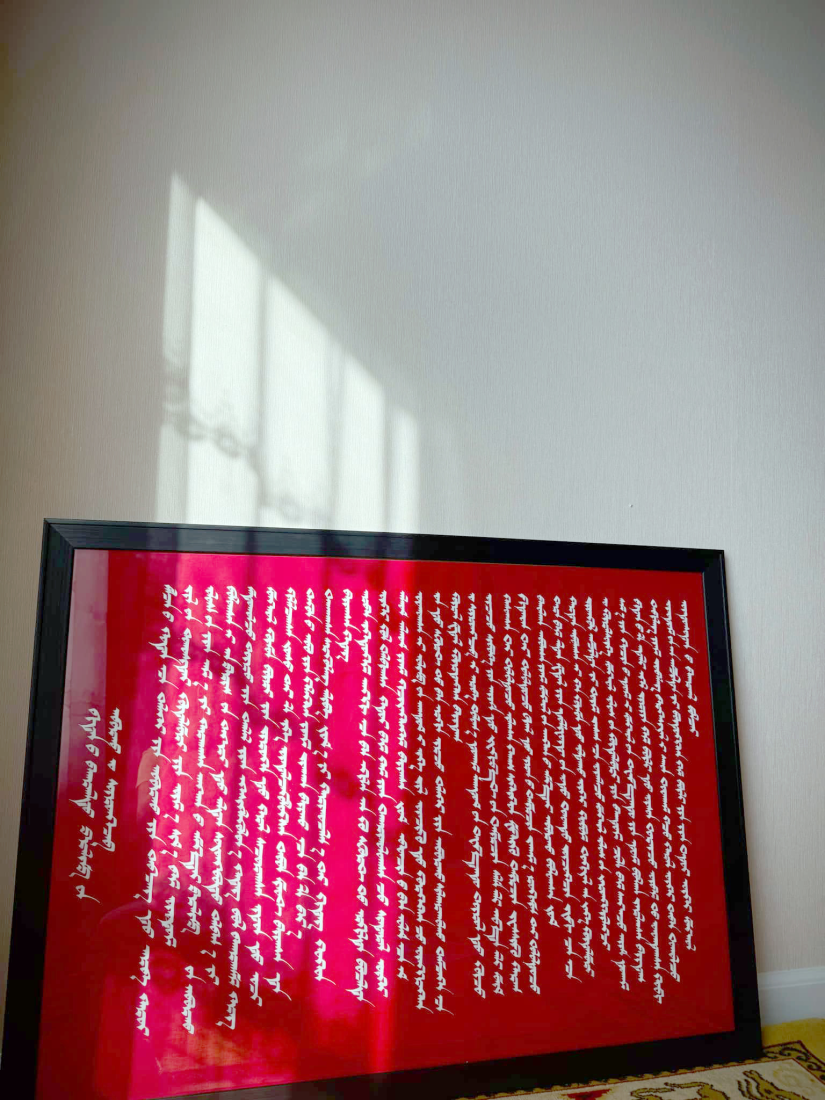
ーー竹筆で書くことは難しかったですか。
簡単だと感じた。一番大事なのは、最初から基本技術をただしく学ぶことであると思った。
ーーモンゴル縦文字を簡単に学ぶ方法をどのように見つけましたか。いつからより深く学び始めましたか。
以前は、他の学校に通っていた。その時は文章力は良かったが、読解力や他の知識が少し足りなかった。しかし、34番学校に転校してきたとき、モンゴル縦文字の先生が私をオリンピアードの準備に取り組ませた。それからモンゴル縦文字の授業がもっと好きになり、上達した。
ーーでは、今後モンゴル語・縦文字を専攻にする考えはありますか。
現時点ではそのような計画はまだない。将来的には法学を学ぶ予定である。
ーーご家族にモンゴル刺繍より作品をつくる方はいますか。
家族に刺繍をする人はいない。家庭科目で先生に技術を教わった。更に、YouTubeで動画を見て独学で学んでいる。
ーー独学で技術を向上させているのは本当に素晴らしいことです...現在、何枚のダリン(刺繍を施した布袋)を作りましたか。
毎年2枚のダリンを作っている。過去3年間で合計6枚のダリンを作った。

ーーコンテストのダリンはどのくらいの期間で作られましたか。
同コンテストに参加するつもりであると伝えたところ、先生に「自分の得意分野を活かして作品を作ってみてはどうか」と言われた。それで、作品のアイデアを考え、11月から制作を始め、約1ヶ月かけてダリンを完成させた。

ーー「モンゴル縦文字競書大会」コンテストの感想を聞かせてください。
同コンテストが全ての人に開かれていることに大変感謝している。誰でも参加できる機会があり、情報が広く普及し、主催者との連絡もスムーズにとれた。
ーー次回のコンテストもまた待っていますね。もちろん、他の部門にも参加するチャンスがありますよ…
ありがとうございます。参加する!他のカテゴリでも、同カテゴリでも自分の作品を更に改善し、挑戦したいと思う。
ーー初めてコンテストに参加して、優勝したことを家族や先生はとても喜んだでしょうね…
結果を聞いたとき、とても嬉しかった。母は特に喜んでくれた。先生もとても支えてくれたので、喜んでいた。
ーー同コンテストに参加したいと考えている同年代の人にメッセージはありますか。
自信をもって、好きなカテゴリに参加してみてね。入賞するか否かは重要ではなく、参加と挑戦は大切である。参加により身につく経験や知識が重要だと思う。






(ウランバートル市、2025年、2月11日、国営モンツァメ通信社)モンゴル国大統領の後援の下で第3回「モンゴルの持続可能な金融フォーラム2024」が開催された。今回、B.ダワーダライ・モンゴル国大統領経済政策顧問に話を伺った。
ーー今回のフォーラムで討論された課題は何ですか。フォーラムの特徴は何でしたか。
11月27~29日にかけてモンゴル国大統領の後援の下で「モンゴルの持続可能な金融フォーラム2024」が「モンゴル国 ―グリーン開発の金融調達」をテーマに開催された。フォーラムは3年目を迎え、大統領府、モンゴル持続可能な金融協会、ハーン銀行、国連モンゴル事務所が共催した。今回のフォーラムに規制機関、民間企業、市民社会の代表など各分野のグリーン開発リーダーたちが参加し、今後の協力と活動について話し合った。モンゴルにとって最優先的な課題は気候変動、土壌劣化、砂漠化である。また、モンゴルは持続可能な開発目標(SDGs)およびパリ協定の下で、2030年までに国際的な義務を果たさなければならない。従って、今回はグリーン開発、グリーン転換、その資金調達について明細に議論した。
ーー新政府は、グリーン開発、グリーン転換などに取り組んでいるのは、時宜を得たと思います。フォーラムでどのような成果が得られましたか。
一番大事であると思うのは、政府が市民や企業に対して、グリーン開発に関する具体的なプロジェクトやプログラムを詳細に説明したことである。今回のフォラームで、政府は市民と企業に対して3つの主要な情報を提供した。
1. 政府はエネルギー分野の改革と再生可能エネルギー・プロジェクトを実施する。
2. 農業分野では「食糧革命」、「ホワイト・ゴールド」、「新協同組合」の3つの国民運動が実施され、現在実施中の農業プロジェクトとプログラムの融資と資金調達において、グリーン開発基準を設定する。
3. 環境に優しく、省エネの住宅を建設した場合、住宅ローンに適用する。
ーーエネルギー、農業、建設分野を重視したのはなぜですか。
モンゴルが排出する温室効果ガスの約90%がこの3分野に関係している。そのため、これらの分野に注力することで、成果を出すことができる。具体的に、現在は家畜100頭のうち6頭だけが集約的に飼育されている。もちろん農業を100%集約的に開発することはできない。私たちモンゴル人は伝統と文化を守るべきである。しかし、特定の割合を環境に優しいものにし、グリーン発展を支援・発展させるのが適切である。つまり、100頭の20頭が農場方式で飼育されれば、環境を保護し、グリーン転換を一段と進めることができる。
ーーモンゴルに適した解決策は何ですか。国際専門家とモンゴル人専門家の提案は何ですか。
モンゴルは2030年までに温室効果ガスの排出量を22.7%に引き下げる目標を設定しており、そのため、二つの政策を実施しなければならない。まず、エネルギー分野の改革と農業分野の強化であり、家畜の頭数を環境に優しく適切なレベルに維持することである。さらに最重要な解決策は、二酸化炭素排出量の多い産業に税金を課すことであり、ビジネスが環境に悪影響を及ぼす場合、高額な税金を支払う原則である。環境への影響が少ない場合は、低額な税金を支払う。他の国々では、同制度を基本政策として採用している。モンゴルにはその規制がまだ導入されてない。モンゴル銀行は課税に関する調査を行っている。これは非常に公平なシステムである。一方、グリーン・ローンを利用した市民や実業家は低金利で長期ローンやインセンティブを受けることができる。
ーー全ての事業の推進力は資金調達である。モンゴルは資金がいくら必要ですか。
2030年までに温室効果ガス排出量を22.7%削減する目標を達成するには、110億米㌦が必要である。この一環、2021年にフレススフ大統領は毎年、環境分野に国内経済の1%に相当する資金を徴収する計画を立てた。つまり、モンゴルの経済が70兆トゥグルグとすれば、7000億トゥグルグがグリーン開発に費やされる。ただし、国家予算だけでなく、民間企業や国際機関など全ての財源を活用する。
ーーモンゴルはグリーン・ファイナンスの調達にどのような方法を利用していますか。
モンゴルに環境分野資金調達の世界ベストプラクティスが導入されている。この一環、世界自然保護基金と共同で「環境永続的な資金調達プログラム」を確立した。現在、国際投資家の助成金により7000万米㌦が投資されている。2030年までに政府と民間企業の協力により、さらに1億米㌦を調達する可能性がある。同基金の目標は、2030年までに特別保護地域の面積を30%に到達させることであり、モンゴルは同目標を法的に保障した。現在、特別保護区の面積は20%である。
ーーリーダーシップにおいて銀行と金融機関がより積極的であるようです。2030年までにグリーン・ローンを10%に到達させるという銀行の目標はどの程度現実的ですか。
銀行と金融機関はそのように取り組まなければいけない。近年、投資家が環境やグリーン開発に投資している。世界がグリーン・ファイナンス基準を採用している。モンゴルも世界的な基準に採用しなければ、国際市場から投資や資金を調達する可能性が低下する。
ーー新政府が自然環境・気候変動省を設立したことは、モンゴルがグリーン・ファイナンスに注力していることの表れですか。
フレススフ大統領は、国連気候変動会議に出席し、環境と気候変動問題に大きな注意を払っている。 オユンエルデネ首相もサウジアラビア王国のリヤド市で開催された国連砂漠化防止条約第16回締約国会議(COP-16)に出席した。さらに、連立内閣は環境観光省を自然環境気候変動省に再編した。近年、自然環境・気候変動に関する法律と法的環境を検討するよう国際機関に言われている。一部の国は「気候変動法」という独立した法律がある。その法律に気候変動に関する全ての内容が含まれており、政府の統治、各省庁の責任、資金調達方法などが盛り込まれている。
ーーお忙しい中、お時間を割いていただき、ありがとうございました。

(ウランバートル市、2025年1月26日、国営モンツァメ通信社)清水武則「モンゴル・日本友好協会」理事長は、2011~2016年にかけて在モンゴル日本国特命全権大使を務めた。数日前、モンゴルを訪問中の清水武則氏に話を伺った。
ーー清水さんは1977年にモンゴルに足を踏み入れました。それ以来約50年間が経過しました。モンゴルを訪れるたびに、最も強く感じることは何ですか。
私は1977年にモンゴルに足を踏み入れた。当時、モンゴル語を学ぶために来たが、残念ながらモンゴルが社会主義国であったため、大学の学生寮で過ごし、教えてもらうことはできなかった。私はベトナムの学生たちと一緒にモンゴル語を勉強した。その当時、生活は貧しかった。それ以降、長年が経過したが、実際にこの期間中にモンゴルで発生した変化を振り返ると素晴らしいという言葉以外は言えない。50年前に、モンゴルが発展のこのレベルに到達するとは想像もしなかった。それ以来、私はモンゴルに4回派遣された。従って、モンゴルは私の第二の故郷となった。
ーー清水さんは在モンゴル日本国大使館に4回派遣され、アタッシェから大使までの職務を務めました。大使としての任務を終了してから8年間が経過しましたが、今回の訪問の目的を伺ってもよろしいでしょうか。
大使としての任務を終えてから、様々な形式でモンゴルと関わってきた。3年前から、私の故郷である大分県の九重町とアルハンガイ県のツェンヘル郡との間で交流を始め、学生交換プログラムを実施することになった。今後、アルハンガイ県と大分県は協力していく予定である。そのため、今回は千葉工業大学で使用されていた550台のiPadを完全に更新し、ウランバートル市とアルハンガイ県の学校に寄贈するために来た。その350台がアルハンガイ県の諸郡の学校に配布される。同活動がモンゴルの教育分野に、ある程度、貢献すると考えている。もちろん、大使としての任務と比べると現在実施している活動はそれほど大したものではない。しかし、今私が目指している最大の目標は、子どもを対象にした活動である。
ーーモンゴルで大使として勤務する際、教育分野で多数のプロジェクトやプログラムを成功裏に実施しました。そもそも、清水さんの活動の中心がなぜ子どもと青年であってきたのでしょうか。
国の発展を加速させるのに人材育成が重要である。モンゴルの人々が健康で教育を受けていれば、どの障害も賢明に乗り越えることができる。そのため、モンゴルは教育分野を最優先にし、注力して取り組むべきであると考えている。
ーー清水さんに関する一つの話を聞いたことがあります。清水さんは、民営化の危機にあった「児童創作センター」の修理に投資を行い、その施設を引き渡したと言われています。当時、「これこそ私がやるべき仕事だ」と思ったと話したそうですが、そのことについてお話しをいただけますか。
ありがとうございます。実は、この話はすっかり忘れていた。同センターに多くの素晴らしい講師が働き、ゲル地区の多数の子どもが教わっていた。従って、その教育活動と周辺の取り組みを維持することが非常に重要であると感じた。そのため、屋根を修理し、引き渡した。当時、かなり努力して成し遂げた仕事の一つである。





(ウランバートル市、2025年1月12日、国営モンツァメ通信社)モンゴル国憲法裁判所の元裁判官であり、法学博士でモンゴル国立大学法学部教授であるTs.サラントヤ氏、憲法裁判所の元裁判官であり、モンゴル弁護士協会憲法委員会委員長で、モンゴル国立大学法学部教授であるSh.ツォグト氏、憲法裁判所の裁判官であり、元法務・内務副大臣で、博士であるV.オドワル氏の3人に「憲法」について話を伺った。
ーーモンゴルは2024年に初代憲法制定の100周年を迎えた。民主的な新憲法(4番目の憲法)は1992年に制定された。この2つの憲法の関連性や特徴をどのように考えていますか。
Ts.サラントヤ氏:1924年、1940年、1960年の憲法は、それぞれの時代の社会的関係の基盤を構築し、国民と政府との関係を調整する役割を果たしていたため、現代憲法の特徴を含んでいる。また、構造や論理の面でも、いずれも一貫したシステムを有する文書であり、成文化された憲法に求められる要件に応じる。上記の3憲法は、モンゴルの現代法制度の発展に大きく貢献したといえる。1992年に民主主義憲法が制定される以前、モンゴルでは裁判所が政府の独立した権限として認識されていなかった。当時、政府に忠誠を誓うことが、裁判所の独立や正義の勝利、侵害された権利の復興よりも重要視されていた。1924年の憲法に裁判官や裁判所に関する規定は一切含まれていなかった。しかし、1940年と1960年の憲法に裁判所と検察庁に関する条項が設けられたが、裁判官は数年ごとに選出される制度が採用された。裁判所と裁判官の独立性に関する概念は、現代のように確立されていなく、裁判や訴訟を公正かつ客観的に決定するための条件は、現在と比較してかなり制限されていた。また、憲法は国家の最上位の権限を有する法律として承認されていたが、その実施と保護は全く言及されなかった。憲法に対する理解と実施は1992年まで抽象的な理論の段階にとどまっていた。一方、新憲法では、市場経済、財産の多様性、思想の多様性、自由などが認められ、人道的かつ市民的で民主的な社会構築が目標として設定された。従って、1992年の憲法第2章に規定された全ての権利と自由が、モンゴル国全土で実現する扉が開かれた。また、他方で、人権や自由を保護するための前提条件を整備するために、政府は自らの行動を憲法に記載された権限の範囲内で行い、そこに定められた権力の分配や制限遵守が、同憲法の特徴を特定する。同件により、1992年の憲法は単に国家の最高法と呼ばれるだけでなく、生活において実際に機能する法基盤を構築したのである。

Sh.ツォグト氏:まず、憲法は政治学、哲学、歴史学、数学など、いくつかの学問分野によって説明される独自の研究対象であることを指摘すべき。憲法の初期理念は、1911年のモンゴル国の5省と上院・下院から開始された。しかし、1924~1960年の憲法に記載された選挙権と被選挙権は、一党制の下での普遍的な選挙性質をもっており、国民は自分自身の政治的指針に基づく真の選択をすることが不可能であった。また、上記の3憲法には現代的に見える多数の権利が盛り込まれていた。例えば、言論、出版、集会、デモの自由、男女平等の権利、労働と休暇の時間を8時間に制限するなど、ポジティブな法的規範が規定されていた。しかし、これらの権利はその目的に応じて制限されていたのである。一方、1992年に制定された民主主義憲法により、モンゴルは過去30年間以上にわたり、政治的な民主主義体制を基盤とした新指導体制の確立を目指してきたと概説できる。

V.オドワル氏:モンゴルは1924年に制定した憲法を1940年と1960年に改正した。社会の変革や改革の理念を反映させた改正が1990年に追加され、これにより以前の憲法の価値観、理念、原則などが変更され始めた。例えば、1990年3月23日に、モンゴル人民共和国の憲法改正案が承認され、1960年の憲法の約10条項に改正が加えられた。前文から「モンゴル人民共和国の政府と社会の指導的な勢力はマルクス・レーニン主義理論である」という表現が削除され、第82条が改訂された。この条文には「モンゴル人民共和国の国民は、人道的かつ民主的で社会主義的な社会を構築する目的、国民の根本的な利益と団結に沿った計画や規則を有する政党や他の公共団体に参加する権利がある」という表現が盛り込まれ、また、様々な思想をもつ政党や市民社会団体が国家を平和的に発展させる基盤が構築された。上記の理念は、1992年の憲法から明確に読み取れる。これは、1911~1924年にかけて、モンゴルが世界の憲法的原則の動向を模索していたことと同様なものである。





(ウランバートル市、2025年1月5日、国営モンツァメ通信社)モンゴル国大統領の管轄下にある言語政策国家委員会のN.ナランゲレル研究者とインタビューを行った。2025年1月1日からモンゴルは千年の歴史をもつモンゴル文字を公式に復活させ、モンゴル語に関する法律の重要な条項が施行されたからである。
ーー2025年が始まり、モンゴルは縦文字を行政の業務に使用し始めた。この取り組みは「モンゴル語に関する法律」に基づいて実施されており、その指導を行っている主要な機関は貴委員会です。
2015年に法律が制定されて以来、同委員会は大規模な構造で同法律の実施を開始した。その過程で、21県の330郡に支部委員会を設立し、10年間にわたって強化し、モンゴル文字の「全国プログラム」を実行した。そして、今日、国民に対して報告を行うことができ、大変嬉しく思っている。
指針と方針に関して「モンゴル文字の全国プログラム3」は2020年にモンゴル政府の決定により承認された。同プログラムは5年間の計画と実施の後、基本的に完了した。「全国プログラム」は4つの目標に基づき、69件の活動を通じて実施する予定であった。「モンゴル語に関する法律」に基づき、モンゴル文字プログラムを実施し、適切な準備が整った上で、行政機関および地方自治体はキリル文字とモンゴル文字の両方で業務を行う。
4つの目標の枠で69件の取り組みの95%が達成されたと見なされ、行政の業務がモンゴル文字の活用により行われるようになった。
ーーモンゴルはいくつの行政機関がありますか?そのいくつがモンゴル文字とキリル文字の両方で業務を行い始めていますか?
2022年に印刷ページの標準が策定された。合計4200箇所の行政機関があり、全職員を対象に研修が実施されてきた。研修の一環、教科書、携帯電話用の電子ツール、教師用のマニュアルが作成された。全国プログラムに基づき、私たちは国家公務員研修プログラムの内容も決定した。
2024年12月27日までの調査によると、モンゴル全国に4200箇所の行政機関があり、その50%、つまり2022箇所の機関がモンゴル文字とキリル文字の両方を活用しているという情報がある。
ーー法律の規定ではキリル文字とモンゴル文字を併用して業務を行うことになっています。一部の機関はすでに2022年から準備を整え、10種類以上の公式文書にキリル文字とモンゴル文字の両方を活用しています。モンゴル文字を復活させることが重要であるということで、モンゴル文字だけで進めていったらどうかという意見もあります。この点についてどう思いますか。
法律の規定に従う。法律では、キリル文字とモンゴル文字を併用すると定められているので、併用しなければ効力をもたない。一部の人々は、二重の紙に印刷して経済的に損失を被るのではないかという問題を提起したが、モンゴル政府は「デジタル・ネイション」プログラムを実施しており、電子的に公式なやり取りができる環境が整っている。従って、経済的な損失はないと考えている。





 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar