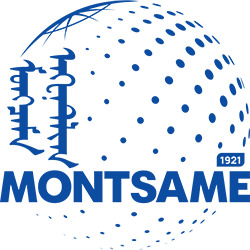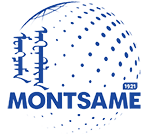セルゲレン氏: “コーセン”は モンゴル語の言葉になった
特集
日本帰国留学生たちの活躍ぶり(シリーズ IV)
1992年、日本へ留学
1993~95年、国際観光専門学校ホテル経営学 科
2000年、国際ビジネス大学会計学科を卒業
現在、IET工業技術大学総長とモンゴル高専校長として活躍中
今回は、JUGAMO会員で、現在教育界で活躍しているセルゲレンさんにご寄稿いただきました。
80年代から産業を支える技術者を養成することなどを目的に、モンゴル政府は多くの若者を日本に留学生として送り、大学や工業高等専門学校(高専)で学ばせてきた。このような若者たちは、今では閣僚、大使、政府高官など国家をリードする人材として活躍している。高専で学んだ卒業生が多く、大きな影響力をもつグループを形成するに至っている。
このような背景の中、実践的技術者養成システムとして「日本式高専システム」を移転しようとする機運が、モンゴル側にも日本側にも高まってきた。モンゴルの日本高専留学生・卒業生が組織する「高専クラブ」及び「モンゴ ルに日本式高専を創る支援の会」のメンバー、日本の企業OB、及び高専教員OB等が中心となって活動がスタートした。活動の当初は、なかなか前に進まない状態が続いたが、その後モンゴル国が二桁の経済成長を示すと、技術者の不足が顕著に表れ、高専創設の動きが表れてきた。
モデルクラス開講
2013年10月 モンゴル工業技術大学(IET)に、笹川平和財団(SPF)支援による「日本式高専教育導入プロジェクト」が立ち上がり、モンゴルに日本式高専を創る支援の会、並びに苫小牧高専と連携協力して「日本式高専教 育モデルクラス」が開講した。SPFの要請で、日本財団が運営する海外シルバー技能 ボランティア協会(NISVA)から西山教授と中西教授が1年間の長期派遣でIETに赴任した。
モデルクラスは、工業高校生の中から試験で選抜した33人からスタートした。日本式高専システムを導入する際、日本式高専は5年間一貫した実践教育を行う学校であり、一般科目と専門科目(実験・実習)が低学年から高学年に かけてくさび状に配置される。しかし、このモデルクラスの授業は、工業高校の授業に高専としての科目、実習を入れ込む形で進められた。専用の教室は特にないため、工業高校の授業が午前中にあると高専の授業は午後に配置、また、実習は2班に分けて、機械系、電気系、建設系の基礎実習を年間ローテーションして全てが受講できるようにした。中西教授が機械系実習を担当し、西山教授が電気系実習を担当した。
モンゴル高専開校
そして、2014年9月、モデ ルクラスを母体にIETに「モ ンゴル高専」が正式に発足した。といっても、高専の制度はないので、高等学校設置の認可を受けて高等学校の教育をしながらプラス高専の教育を入れ込むことから始まった。先ず、日本式であるので、入学式を室内で行う、オリエンテーションを泊付で1年生全員が参加する、など目に見える形で日本式をアピールしていった。
2014年9月、IET附属モンゴル高専のほかに、国立科学技術大学附属工科大学(ガンバヤル校長)と新モンゴル学園附属新モンゴル高専(ブヤンジャルガル校長)の2校が開校した。この動きは、2012年7月政権が民主党に代わって、日本の高専を卒業したガントムル教育科学大臣が就任してからのことで、大きな影響を及ぼしている。3校には同じような学科があり、教科書の翻訳、機材の調達、学生や教員の研修、専門家の派遣などで、お互いに協力できるところは協力しようと教育科学省公認のNGO法人「モンゴル高専教育センター」を立ち上げた。NGOはガントムル大臣の指示するところにより高専に関係した高等教育法の立案に協力し、その甲斐もあって2016年4月、高専を高等教育機関に位置づけた「高等教育に関する法律」が制定された。法律には、 エンジニア、テクノロジストの育成を行うテクノロジーカレッジが表記されている。これが高専に該当するもので、モンゴルでは「КООСЭН」とよんでいる。
モデルクラスは、工業高校生の中から試験で選抜した33人からスタートした。日本式高専システムを導入する際、日本式高専は5年間一貫した実践教育を行う学校であり、一般科目と専門科目(実験・実習)が低学年から高学年に かけてくさび状に配置される。しかし、このモデルクラスの授業は、工業高校の授業に高専としての科目、実習を入れ込む形で進められた。専用の教室は特にないため、工業高校の授業が午前中にあると高専の授業は午後に配置、また、実習は2班に分けて、機械系、電気系、建設系の基礎実習を年間ローテーションして全てが受講できるようにした。中西教授が機械系実習を担当し、西山教授が電気系実習を担当した。
モンゴル高専開校
そして、2014年9月、モデ ルクラスを母体にIETに「モ ンゴル高専」が正式に発足した。といっても、高専の制度はないので、高等学校設置の認可を受けて高等学校の教育をしながらプラス高専の教育を入れ込むことから始まった。先ず、日本式であるので、入学式を室内で行う、オリエンテーションを泊付で1年生全員が参加する、など目に見える形で日本式をアピールしていった。
2014年9月、IET附属モンゴル高専のほかに、国立科学技術大学附属工科大学(ガンバヤル校長)と新モンゴル学園附属新モンゴル高専(ブヤンジャルガル校長)の2校が開校した。この動きは、2012年7月政権が民主党に代わって、日本の高専を卒業したガントムル教育科学大臣が就任してからのことで、大きな影響を及ぼしている。3校には同じような学科があり、教科書の翻訳、機材の調達、学生や教員の研修、専門家の派遣などで、お互いに協力できるところは協力しようと教育科学省公認のNGO法人「モンゴル高専教育センター」を立ち上げた。NGOはガントムル大臣の指示するところにより高専に関係した高等教育法の立案に協力し、その甲斐もあって2016年4月、高専を高等教育機関に位置づけた「高等教育に関する法律」が制定された。法律には、 エンジニア、テクノロジストの育成を行うテクノロジーカレッジが表記されている。これが高専に該当するもので、モンゴルでは「КООСЭН」とよんでいる。
 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar