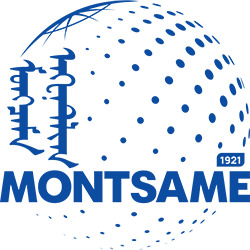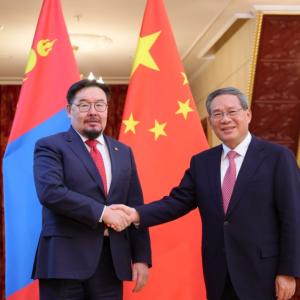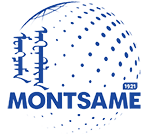ボルガントヤ財務副大臣:大型開発事業なしでは国内経済の拡大を考えられません
特集
2018年度におけるモンゴル経済情勢及び執行される課税などについて、Kh.ボルガントヤ財務副大臣にインタビューを行った。
――世間は新年早々からの増税措置の執行を巡って政府に対する批判を強めているが、増税に関する見直しはありますか。
モンゴルは、2016年度第三四半期における経済がマイナス成長で対外債務に悩まされていました。国際通貨基金(IMF)はモンゴルに対して消費税の税率引上げを含む国家歳入の増額を要請していました。政府も、消費税の税率引き上げ装置が一般家庭への直撃が大きい、としてIMFとの妥協を探っていました。増税措置は、簡単な決断ではありません。収入額に応じた累進課税は労働者の94%に当たる所得が150万トゥグルグ未満のものに対して影響がありません。むしろ、彼の税負担が毎月3000トゥグルグ緩和されます。2017年度は所得控除額が約8万4千トゥグルグであったが、2018年度はその額が約12万トゥグルグの増額になりました。現在は、収入が150 万トゥグルグ以上になる納税者は約5万2000人がいます。これは労働者総数の6%に当たり、150万~250万トゥグルグの収入がある者は3.9%、250 万~350万トゥグルグの収入がある者は0.6%、350万トゥグ ルグ以上収入の者は1.5%になります。この増税措置は、一 定額以上になった場合にその超過金額に対してのみ、より高い税率を適用する超過累進税率方式を採用しています。 例えば、250万トゥグルグの収入がある者は、その150万トゥグルグに対して10%、超過分に対して15%の税率で納税する仕組みです。納税額は4万 7000トゥグルグ増えるということです。税率引上げの際には一般国民に負担を強いら れないように配慮しました。
――世界各国における所得税 の仕組みとはどうでしょうか。
累進課税を採用する国が多くて、国家歳入に占める割合 も大きいです。モンゴルの場合は8%を占めています。中国 は45%までの7つの段階による 累進課税を採用しています。 スリランカも一人当たり国内 総生産高がモンゴルと同じだ が、24%までの6段階の累進課税を実施しています。モンゴ ルも2007年以前は40%までの税率による累進課税を採用していました。それ以降、国民の生活水準や購買力などを配慮して10%の税率を執行しました。
――国民は税率引上げを受 け入れる代わりに、国家予算 の合理的かつ適正な運用を求 めらるのでは。
確かに、納税者による税金 が適正な運用されている場合 は彼らが納税に意欲を示す が、逆に悪しき者の私腹を増 やすなら、課税を支払わないとの投稿がソーシャル・ネッ トワークで目立ちます。政府は、課税の増額に応じて公共 財に対する出費も増やす方向で調整を進めています。政府は学校や幼稚園に関する問題を重視して、2018年度にその解決を図ろうとしています。3 交代制学校をなくすことや幼稚園ない地区における新設などです。この制度は、富の再分配の観点に立ち、所得の多いものから所得の低い社会保障を必要とするものに割り当てる機能を持っています。
――2018年度国家予算法の関 連で鉱物資源に関する法律が 改正されした。その可決の際 には、ライセンスに関する闇 取引を明かすとは。
2018年度国家予算法に関連して一部の法律に対して改正が行われました。国は鉱業及び鉱物資源に関するライセンスや土地売買などの取引に対して適切な税金を課してない事実を重く受け止め、規制にかかったわけです。2018年度国家歳入には、約360億トゥグルグの納税を見込んでいます。2007年から執行された現行法では、鉱物資源に関するライセンスの譲渡に対して税率が30%という高い課税を課していました。しかし、取引当事者らは税逃れを探り、税収が思うほどできなかったのです。特に、オフショア地域における会社設立とそれを経由した取引を行っています。モンゴルは、外国で行われた取引に対して税金を課されることができませんでした。こうした問題への解決と調整を今回の法律改正で図りました。
――鉱業は増税措置に対する 反対が根強いようですが、これについてどう思いますか。
発行された鉱業に関するライセンスが約3000件です。しかし、実際に活用されているのはほんの一握りと言って過言ではありません。同法律の発効につき、2つのガイドラインが定められました。一つは当該ライセンスに対する価値評価の計算法に関するガイドラインです。もう一つは法人税及び鉱物資源に関する法律に基づくライセンス譲渡取引に対する課税に関するガイドラインです。この法律で規制も強化されており、脱税及び虚偽申告に関する疑いがある 場合、当該ライセンスの没収を含む罰則も行うとしました。
――当該ライセンスに関す る闇取引を明かす意義とは。
これまでに鉱業ライセンスの譲渡による納金額は少なく、国民がその恩恵を受けることがなかったわけです。例を挙げると、オユトルゴイ鉱山に関する権利がアイヴァンホー・マインズからリオ・テ ィントに譲渡された際には、モンゴルに一銭も納税されてなかったです。この取引に 対して30%の税金を課されたが、租税法における相反などによって実現されなかったわけです。今回の法律改正で、当該ライセンス取引に対して課税できる仕組みができました。要するには、これらの見直しでモンゴルの鉱物資源に対する真の主が誰かが明確になるわけです。
――税率30%措置が発行され たすべてのライセンスに適用されますか。
当該ライセンス譲渡に係る税金に関しては、その最大株主がその持ち分に対して取引を行う際に支払う仕組みとなっています。一方、小口の株主に対して適用されません。
――モンゴルはほかの資源国のような税制を採用したと考えていいですか。
税制導入に関しては、国際機関から2012年に勧められていました。国際通貨基金や世界銀行、国連の二重課税回避に関するモデル条約などがあります。そのため、ほかの国で執行されている法律を検討し、同ガイドラインを採用しました。収入源がどこにあるかによって税金を課すことは ごく当たり前のことです。モンゴルは鉱業に対してそういった権利があるはずです。
――鉱業関連企業は、そのラ イセンスを担保にして商業銀行 から借入を行うケースがありま す。債務不履行による抵当権の 実行の際に課税が生じますか。
抵当権の実行の際には、譲渡に係る課税が生じます。商業銀行も貸付を行う際、その債務履行能力によるリスク負担 を担うこととなります。
――欧州連合は、モンゴルを租税回避地ブラックリストに指 定しました。これによってどの ような影響がありますか?
2015年に開催されたアンタ ルヤ・サミットでG20は国際課税で税源浸食と利益移転(BEPS)に関して合意しまし た。欧州連合(EU)からは、 モンゴル財務省と国税庁に対して自動的情報交換の枠組みに加わるような要請がありました。モンゴルは資金洗浄や租税回避などの金融犯罪に対する世界各国の行動に積極的に関わっています。欧州連合の要請に対しては、モンゴルの租税法のみならず関連法の改正を実施する必要があるために法の改正を含んで検討を行う時間がほしい、と回答。 モンゴルはBEPS枠組みへの加 入に関して技術的な問題があります。同省は租税の透明性及び情報交換に関する世界フォーラムへの加入を全面的に支持しており、閣議及び国会における公式な議論から欧州連合と協議する考えです。
――租税回避地ブラックリス トに指定された国々に対する経済制裁がされるとの噂があ りますが、これについてどう ですか?
EUによるバラックリストが初めてのことです。自動的情報交換の枠組みに加わることで、バラックリストから除名されるという基本的な条件があります。政府は基本的に加入を支持し、CH.フレルバートル財務大臣もモンゴル政府の見解をEUに伝えました。EUからも回答があったために経済制裁はないと思います。
――2018年におけるモンゴル 経済情勢についてどうお考え でしょうか。
経済回復は順調に進んでいます。いくつかの要因があります。まずは、主産業の生産品となる石炭と銅の国際相場が良い影響をもたらしています。そのほか、IMF支援プログ ラムで歳出削減と歳入拡大に関する諸取組を実施しています。これらの取組は、外国人投資家の信頼回復につながっ ています。ホラルダイ債及びゲレゲ債は堅調継続がその証です。さらに、モンゴルに対 する信用格付けも改善されました。世界の信用格付け機関は、モンゴル輸出品の国際相場における価格上昇を要因で引上げしない、むしろ対外債務による負担と適切な政策など中期的な要因を配慮しています。モンゴル経済が依然として脆弱です。国際機関もそう指摘しています。国内経済拡大及び歳出削減は主な取り組みです。大型開発事業なしでは、国内経済の拡大を考えられません。政府もこうした事業の発動を巡って取り組んでいます。結果は近い頃に現れるはずです。
WWW.NEWS.MN
記者:Sh.オユンチメグ
記者:Sh.オユンチメグ
 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar