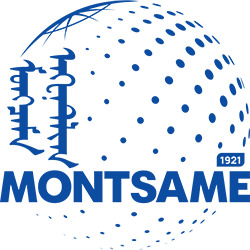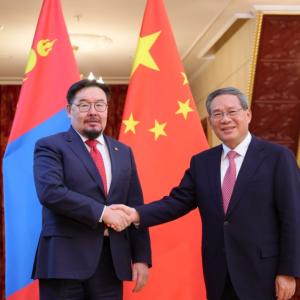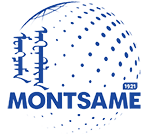吹雪に立ち向かうラクダ飼育者の一日
特集
I.
モンゴルは現在、世界的に昔ながらの遊牧生活様式を保持してきた唯一の国である。地方の厳しい状況の中で古代から受け継いできた牧畜業を営んでいる人々は未だに多い。五畜(馬・ラクダ・牛・羊・山羊)は四季にまたがり植物の生育状況に合わせて肥えるので、牧草地の良さを探し移動しなけばならない。五畜の一つとなるフタコブラクダはモンゴルのゴビ砂漠にのみ飼育されている。そこで、国営モンツァメ通信社の取材団はモンゴルのゴビ地帯のラクダ飼育者の代表となるドンドゴビ県ウルジート郡に住む「1000頭の遊牧民」、「県の優秀なラクダ飼育者」のオトゴン・ジャルガルサイハンさんの一日を取材した。
ゴビへの辿り道は遠くて静かで、行き先々の家の主は親しみを感じるが以前会ったことのない見知らぬ人物である。都会の忙し気なリズムから離れ、ゴビの広大な平原に辿り行くと、2月の暖かい日々が既に訪れ、平穏が植物や土の奥深くへ浸み込んでいた。このような日々の夕暮れ時に、見知らぬジャルガルサイハンさんの家に辿り着いた。つい昨夜、星空に満たされ、静寂に包まれていたのが、翌朝になると吹雪が舞っていた。ジャルガルサイハンさんの家を一時訪れていた従妹のT.サイハンツェツェグさんが夜明けと競い、火を焚き、ラクダのミルクでおいしいミルクティーを沸かし、家の主と取材団の我々にご馳走してくれた。

ゲルの外で家畜は吹雪をも気にせず、暖かい小屋でゆっくりと草を食んで横たわり牧草地へ行きそうもない。家主のジャルガルサイハンさんは「夜明けから吹雪が始まった。今年の冬は一度も雪が降っていない。ツァガーン・サルが過ぎるまで家畜は水に困らなくて嬉しい。今日は天気の様子を見ながら家畜の放牧を決める」と語ってくれた。ジャルガルサイハンさんの家は、遊牧民族が大昔から飼育してきた五畜を飼育している。1000頭余りの山羊と羊、牛40頭、馬100頭、ラクダ500頭余り飼っている。昨年100匹の子ラクダを無事に育てた。ゲルの外にいるのは2歳の子ラクダと雌ラクダだという。他のラクダは自由に放牧し、吹雪の中、彼らを見つけにくい。「ラクダはとても賢い家畜。一頭二頭では頭数が増えない。群れになってから頭数が増える、人に対して親しみを持つ動物。今放牧先のどこかの丘のふもとで群れになって横たわっているでしょう」と、ジャルガルサイハンさんが話す。彼の父親はモンゴル国功労遊牧民のKh.オトゴンさんだ。1990年に「千頭の遊牧民」、2002年に「モンゴル国功労遊牧民」、県の3回の「優勝な遊牧民」に選ばれていたのを、オトゴンさんの長男のO.テグシバヤルさんが、私たちを迎える時、誇らしげに話してくれた。今、父親のオトゴンさんはウランバートルの保養所で治療を受けているという。ジャルガルサイハンさんは末っ子で兄弟は10人。兄弟の4人が父親の遊牧民的な遺伝を受け継いでいる。

II.
朝食の後もラクダは立ち上がろうともしない。吹雪がおさまり、天気が回復しようとすればラクダは自ら立ち、雪を振り落とすという。ゴビの遊牧民は家畜の性格や行動を観察しながら、自然や気象の変更を良く推測できる。
ジャルガルサイハンさんは数杯のお茶を飲んだ後、小屋へ向かい、2パッケージの干し草を下ろし、放牧されていない山羊や羊に与えた。彼の末っ子のJ.エンフバヤル君も同行し、ぼっちゃりした手で数本の草を握り、山羊にあげているのを見るととてもかわいい。ジャルガルサイハンさんは小屋にいる家畜に草をやってから、ゲルに入ると既にテレビが着いている。ゲルの奥にあるテレビでは国内だけでなく、海外の数多くのチャンネルを衛生アンテナで問題なく見られるが、遊牧民には日常的に見る暇はなかなかない。だが、今回ジャルガルサイハンさんの長女のJ.エンフジンさんがオンライン授業を受けている。娘さんは今年小学校3年生。世界的な新型コロナウイルス感染の影響を受け、モンゴル政府は検疫措置を取り、義務教育学校や大学は休校とし、その代わりにオンライン授業が実施されている。エンフジンさんはオンライン授業の時刻を良く覚え、宿題もちゃんとしている。なお、弟のJ.エルフバヤル君は5歳の幼稚園児だが、休園で家にいる。


娘さんが勉強中、外からお客さんが訪れてきた。冬の寒さ、吹雪に立ち向かいながらラクダに乗って走ってきたのがジャルガルサイハンさんの従妹のE.エルデネバヤルさんだった。エルデネバヤルさんにお茶を出そうとしたところ、彼はデール(民族衣装)の胸のところから黄色袋に入れた自分用の銀製茶碗を出して渡した。モンゴル人にとっては茶碗は単にご飯の入れものではない。「生きてさえいれば金製茶碗から水
を飲む」、「茶碗の返しはその日に、馬の返しはその年に」ということわざからみると、茶碗は日常生活と深く結び付き象徴的に考えられてきたのが明らかであろう。エルデネバヤルさんに茶碗のことを聞くと、「昔からモンゴル人は茶碗を特別の袋に入れ、他人に渡さず、自分用に使ってきた宝ものだった。ロシア人は茶碗の底に銀コインを入れてお茶を飲んでいたということを聞いたことはあるが、モンゴル人は銀製茶碗を使っているよ。現在、各国で様々な感染病が発生している(コロナウイルスを言っている)。こんな時に自分用の茶碗を持って飲むのがずっと正しいのではないかと思う」と話した。話の中、家主の兄のテグシバヤルさんも「うちの父も若い時、自分用の模様付きのおしゃれな袋に茶碗を入れて持っていた」と話した。

昔から受け継がれてきた習慣のユニークな文化が現在復活し、お互いに最高のプレゼントとなる「口が上向いている(将来栄える)入れ物となる銀製茶碗」を贈るようになった。また、自分用の茶碗を持ったゴビの男を見ると、昔の知人と出会ったように親しみを感じた。果てしのないモンゴルのゴビで移動生活が絶え間なく続くように、忘れられつつある習慣もこのように復活して続けられている。

III.
当日は吹雪のため、ジャルガルサイハンさんが近くの隣人から雌ラクダの乳搾りに人の手を求め、電話をかけた。遠く離れたゴビ砂漠ではGモバイル移動体通信事業者の携帯電話が生活に大きな役割を果たしている。そこへ、ジャルガルサイハンさんの兄の奥さんと娘さんが手伝いに来た。

彼らは吹雪を気にせず、乳搾りの準備をして木製と金属製のバケツを持って外に出た。トロム(2歳の子ラクダ)を一頭ずつ小屋から取り出し、少し乳を飲ませた後、乳搾りを始めた。ラクダのミルクは脂が多く、様々な病気を癒すを力を持つ。例えば、ラクダのミルクは悪性がんの細胞を減らし進行を抑制するほか、糖尿病の治療にも一番効く。ラクダの乳糖は他の家畜より多いが、母乳と比べると2.3%少ない。乳糖は、酵素およびビタミンと共に胃に入って乳酸に変わり、酸性環境を作り出す。従って病気や腐敗菌を殺し、心臓、肝臓、腎臓の平常な働きを良くする特徴を持つ。ゲルの外にいる40頭余りのラクダの乳を3人の女性が一時間も経たないうちに搾り終えた。これはゴビで生きる女性の日常生活のリズムになっていることを表している。

ゲルの外にいる40頭余りのラクダの乳を3人の女性が一時間も経たないうちに搾り終えた。これはゴビで生きる女性の日常生活のリズムになっていることを表している。ジャルガルサイハンさんの家は、冬場はゲルの外にいるラクダから一日20㍑の乳を搾る。家庭用のミルクとして使うほか、それを集め、ホールモグ(ラクダ乳酒)を作って売る。冬の3か月では平均2㌧のホールモグを販売し、家庭収入の一部に充当させる。また、ミルクでアーロル(乳酸菌固形ヨーグルト)などの乳製品も作る。ラクダのアーロルはモンゴルでは最も高く、1㌔およそ4万トゥグルグ(=1600円)になる。乳搾りの時間が終わり、女性たちは家に向かう。

一方、ジャルガルサイハンさんはラクダを牧草地に放牧する。寝転がしの場所から離れたラクダは吹風の方向に向かって歩き出した。それは動物の本性であろう。しかし、飼い主さんは「ハー、フッジ」と叫びながら、方向を変え、南西へ誘導した。「ラクダに方向を教えて放牧してしまえば、このような大雪の時でもどこへ行って草を食うかが分かっている」と彼が話した。「ラクダは予知能力が高い家畜なの?」と聞くと、一瞬無口に歩いていた飼い主さんは「ゴビは風や嵐が多いというのを誰でも知っている。冬の最後の月は暖かいが、一瞬に吹雪が吹くのが普通。長年、ゴビでラクダを放牧している僕でも吹雪の時には迷うことがある。道に迷い、家を見つけられない時、ラクダの紐を緩くしておくと、ゆっくりと走って家を見つけるのだ。僕だけではなく、他の遊牧民にもこのようなことが多くあった。だから、ラクダはやはり予知が優れている動物でしょう」と話してくれた。次の飼い主さんは羊と山羊を牧草地へ放牧した。もし、吹雪がなければ、井戸で家畜に水やりの仕事が増えるはずだったという。


乳搾りの作業が終わり、遊牧民は火の上にある料理の出来上がるのを待ち、色々と話し合う。話の大半はラクダの群れや、天気についてだが、苦情を話すことはめったにない。「絶望に涙はない」というように、いくらでも自然の厳しさと立ち向かったにも関わらず、平穏で辛抱強い人々だからこそ、広大なゴビに住み慣れているのであろう、そう思った。大作業の後、暖かい会話と微笑みでゲルが一瞬にして溢れる。それが最高の雰囲気。
IV.
午後に吹雪が収まり、遠くが見えるようになると、家主のジャルガルサイハンさんが牧草地へ向かったラクダの一部の群れを確認に行った。私たちも付いて行った。ここは500頭のラクダを飼育している。ラクダは一カ所に集まるのではなく、それぞれ一部の群れになって放牧しているという。

ここは年間2500kgのウールを刈り取っている。また400頭の山羊から春に200kgのカシミヤを刈り取る。昨年、ラクダウール1kg当たり6000トゥグルグ(=240円)、カシミヤ1kg7万~8万トゥグルグ(=2800~3200円)だった。また、ゴビではラクダの肉を食肉に使っている。種ラクダの体重は700~800kg、肉は500kg、なお、雄ラクダは300kg~400kg。ラクダ肉は1kg4000トゥグルグ(=160円)で販売している。成熟した雄ラクダは160万トゥグルグ(=6万4000円)、体格が大きければ200万トゥグルグ(=8万円)にもなる。ジャルガルサイハンさんの家は家畜原料、食肉、乳製品から少なからず収入を得て、金銭的支障なく生活を送っているのがみられる。牧草地へ向かい、家畜の原料やミルク価格について話す途中、家主のジャルガルサイハンの兄のテグシバヤルさんが「夕飯にラクダのあばら肉と干し肉入りのお米入りミルクティー作ってあげよう」と言った。
まもなく、ゴビの丘の中腹からジャルガルサイハンのラクダの一部の群れがゆっくりと放牧しているのが見えてきた。取材の主役となるジャルガルサイハンさんといとこのエルデネバヤルさんがラクダの群れを回りながら、それぞれ、一頭の雄ラクダに縄をかけて捕まえ、乗ってきたラクダに乗り換えた。たまに、最近乗っていないラクダに訓練を忘れせないように乗り換えることがあるのだという。牧草地のラクダを確認しながらジャルガルサイハンさんが「父は私を家畜を愛する人間として育ててくれた。『ラクダを飼育する者は種ラクダの性格に精通している』というように、私も他の家畜よりラクダをより知るようになっている。ラクダは低い標高地点で繁殖する特徴を持っているので、ゴビの私たちには大変有益な動物である。夜と昼を問わず遠くを眺め続け、匂いに敏感なラクダは、井戸やゲル跡に漂う匂いも30キロ先から感知できる能力を持っている」とラクダの特徴を話してくれた。
ラクダの牧草地から戻る時、日が既に丘の裏へ沈み始めていた。ゴビの冬の森林地帯より、日没は遅いが、遊牧民の忙しい生活があっと言う間に夕暮れに溶け込んだ。私たちもゲルに向かった。ラクダの群れは盆地の寒さを気にしないで、ゆっくりと草を食べながら後ろに残った。

V.
既に小屋にいて、雌ラクダだけが帰ってこなかった。小屋から子ラクダの鳴き声が聞こえる。ジャルガルサイハンさんは、「雌ラクダは夜遅くなってから帰ってくる」
と言いながら、羊と山羊の様子を見てから「半分はまだいない。近くに残っているのでは」と言い、探しにいった。この際中、兄のテグシバヤルさんがおいしいお米入りミルクティーを作ってくれた。また、ホーホールモグにミルクを加え薄めに沸かしてくれた。そとは既に暗くなり、家主のジャルガルサイハンさんが戻ってきた。牧草地に残った羊と山羊は近くの井戸に行っていたという。家主さんがデールを脱ぎ、晩ご
飯をごちそうしている時に、昼に聞き残していた双子ラクダについての話を続けた。彼は「双子ラクダについてはたまにテレビで見るが、長年ラクダを飼育している私にも双子ラクダを見たことはない。だから良く知らない。しかし、去年、羊の色をしている子ラクダが生まれたよ」と答え、写真を見せてくれた。砂の丘の頂上を肌足で走り回る子どもたちとラクダの鳴き声の中でジャルガルサイハンさんは生まれ育ったのだ。言葉は少ないが、考えを素直に言う彼と一日を過ごした。吹雪の寒さを気にせず「まだ暖かいよ」といつも言い、お客が訪れると朝一に起き上がり、お茶を沸かしてくれるラクダ飼育者の冬の日々がこのように流れる。そして、生活は平穏に流れる。
取材を終えて、ジャルガルサイハンさんに感謝の気持ち表し、記念写真を共に撮って、道を良く教えてもらい帰路についた。





取材:B.アルタンホヤグ
Sh.バトボルド
写真撮影:N.バトバヤル
 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar