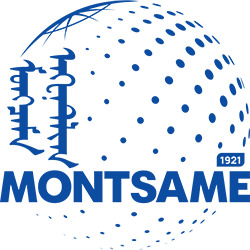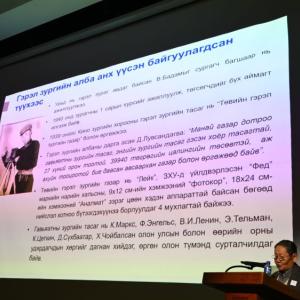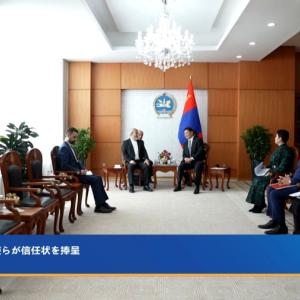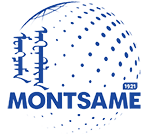バーサンダシ氏:研究者は国の宝
特集
日本帰国留学生たちの活躍ぶり(シリーズ V)
チョイジル・バーサンダシ氏(49歳)
2001年、日本・東京工業大学へ留学。同大学工学修士と博士取得。
現在、モンゴル科学技術大学研究イノベーション担当副学長として活躍中。
――まず、モンゴルでの活動についての話から始めたいと思います。
現在、モンゴル科学技術大学で研究イノベーション担当副学長として努めています。
もともとの専門は機械工学ですし、最近、日本をはじめ韓国、ドイツからの中古車が増えていますのでモンゴル自動車リサイクル会MoARAを設立し、会長として活動の幅も広げようと努めています。
――現在務めているモンゴル科学技術大学研究イノベーション担当副学長という仕事の意義について具体的に教えてください。
本大学は工学、サイエンスとビジネスマネジメントや人文の育成をメインにして発展して来たわけですが、これからの方針としては研究大学を目指して大学院やベンチャー活動も広げていきます。モンゴル政府も研究大学を支援する政策を実施予定です。教育だけでは国の発展を促進する人材は育てません。研究と教育の両方をもって励むことです。
2014年から実行中である日本の円借款事業「高等工業教育MJEED」プロジェクトの共同研究も担当しています。日本の各大学との共同研究をつなげる役割りが大きいです。そして日本の企業とのつながりを産学官を生かして実現させるところが重要です。2012年に出来たモンゴルイノベーション法の実行にも国際的な活動が重要とされています。モンゴルテクノポリス会も設立し、役割りを拡大するNPO活動も行っています。
――日本への留学とは大きな決断だったと思います。なにかきっかけがありましたらぜひ聞かせていただきたいのですが。
1990年代から大学院生でモンゴルの大学から留学が出来るようになりました。その頃からモンゴル科技大も修士課程が始まり我々は最初の院生として勉強していました。一緒に修士課程を修了した仲間の一人が文部省留学で行って、日本の大学で勉強や研究が出来る環境について教えて貰いました。それが一番に影響して試験準備に励むようになった。もちろんその頃JICAを通して日本の支援が広がっていましたし、バガノール高山でコマツのダンプトラックやショベルカーが入り、女性でも運転しやすいことを見学し、日本の技術や研究成果が新聞やテレビで沢山報道されていたのもより興味を深めてくれたと思います。
――モンゴル商工会議所から「Greenpreneur 2012」賞を受賞されたそうですが、それについて教えてください。
日本から戻った頃、日本のJWSTechnicaという電解水技術の会社が大学に技術紹介に来ていて、化学製品より環境にやさしい、農業から家畜、そして病院での殺菌能力など幅広い分野でイノベーション起こすメリットがあることに驚いて、ぜひモンゴル科技大で研究開発を進め、ベンチャーを起こしたいと思いました。研究開発が始まり、ウランバートル市が抱えているスモッグや水処理所の消臭にも効果があることを証明しました。
中国から沢山輸入されている環境を汚す化学物質を出来るだけ減らし、製品として安く出来ることが特徴です。
――現在の研究活動を教えてください。
もともと東工大でレーザー加工とレーザー還元の研究を行っていました。特にマグネシウム金属のエネルギーを蓄える材料として太陽から発するレーザー光で還元し、そのどこにでも豊かにあるところを生かし、リサイクル出来ることに注目していました。来年からADB支援で設立予定のレーザー研究センターでこの研究を続ける予定です。
そしてレーザー光で推進出来る無人飛行機の研究も東工大でやっていましたので今、長岡技科大と共同で無人飛行機の研究開発を行っています。モンゴルは広いけど、運送インフラがまだ出来てないところが多いし、草原の家事やゾド雪害で悩む遊牧民に役に立てるということで、共同研究のタイトルを「SkyInfra」と名付けています。高度が5kmまでの無人飛行機だけではありません、地上から10~50kmに存在する成層圏まで上げる風船、そしてそれにつけてリモートセンシング装置の開発研究にも広げています。
――再生可能エネルギーの開発は今が一番旬かと思いますが、それについてどう思いますか?
幸いモンゴルは再生可能エネルギー資源が豊かな国です。しかし不安定なため、このエネルギーをどれだけ安く、どこでも使えるように蓄積できるかが問題です。最近、トヨタのハイブリッド車が増え、それのリチウムやニッケル電池を遊牧生活に利用できるかも大事です。自動車リサイクルを行っているMoARAメンバーのIMAI‐AMKA社をはじめいくつかの企業がその電池を買い取って集めていますが、残念なことはそれに関して正しくない説がテレビで報道されているようでく。研究者として科学に基づく説明が重要ですので、日本側の研究者たちの活躍を期待しています。
モンゴルの資源を利用して将来性が高い電池技術を第一産業として発展させるのが一番です。日本はこの分野では最先端の国ですし、これからの研究開発や新しい産業を起こすにも最大のパートナーだと思います。
――研究一筋で生きることとは?
研究者は国の宝です。資源が豊富だけど労働者が少ないモンゴルにとって、知識経済の発展は重要です。最近の研究調査で分かっているのは温暖化によって砂漠化が猛スピードで広がっている。遊牧民族の生活にも影響して行くとわが国の文化、経済にも被害が及ぶ。モンゴルだけではなく中国とロシアにも良いことはないでしょう。モンゴル人口の7割が35歳までの若者です。昔から若い内に勉強に励むようにと教わってきた国民です。大学希望者数も人口の割合で言うと少なくありません。ソ連教育の良いところを生かして若い研究者を育てていくためには、大学や研究機関の役割りが大きいです。イノベーションのエコシステムが出来ていくうちに、研究者や起業家の良い役割分担が出来て、今よりももっと研究一筋で生きる人たちが増えるでしょう。
――いろいろ教えていただき、ありがとうございました。今後のご活躍を期待しております。
チョイジル・バーサンダシ氏(49歳)
2001年、日本・東京工業大学へ留学。同大学工学修士と博士取得。
現在、モンゴル科学技術大学研究イノベーション担当副学長として活躍中。
――まず、モンゴルでの活動についての話から始めたいと思います。
現在、モンゴル科学技術大学で研究イノベーション担当副学長として努めています。
もともとの専門は機械工学ですし、最近、日本をはじめ韓国、ドイツからの中古車が増えていますのでモンゴル自動車リサイクル会MoARAを設立し、会長として活動の幅も広げようと努めています。
――現在務めているモンゴル科学技術大学研究イノベーション担当副学長という仕事の意義について具体的に教えてください。
本大学は工学、サイエンスとビジネスマネジメントや人文の育成をメインにして発展して来たわけですが、これからの方針としては研究大学を目指して大学院やベンチャー活動も広げていきます。モンゴル政府も研究大学を支援する政策を実施予定です。教育だけでは国の発展を促進する人材は育てません。研究と教育の両方をもって励むことです。
2014年から実行中である日本の円借款事業「高等工業教育MJEED」プロジェクトの共同研究も担当しています。日本の各大学との共同研究をつなげる役割りが大きいです。そして日本の企業とのつながりを産学官を生かして実現させるところが重要です。2012年に出来たモンゴルイノベーション法の実行にも国際的な活動が重要とされています。モンゴルテクノポリス会も設立し、役割りを拡大するNPO活動も行っています。
――日本への留学とは大きな決断だったと思います。なにかきっかけがありましたらぜひ聞かせていただきたいのですが。
1990年代から大学院生でモンゴルの大学から留学が出来るようになりました。その頃からモンゴル科技大も修士課程が始まり我々は最初の院生として勉強していました。一緒に修士課程を修了した仲間の一人が文部省留学で行って、日本の大学で勉強や研究が出来る環境について教えて貰いました。それが一番に影響して試験準備に励むようになった。もちろんその頃JICAを通して日本の支援が広がっていましたし、バガノール高山でコマツのダンプトラックやショベルカーが入り、女性でも運転しやすいことを見学し、日本の技術や研究成果が新聞やテレビで沢山報道されていたのもより興味を深めてくれたと思います。
――モンゴル商工会議所から「Greenpreneur 2012」賞を受賞されたそうですが、それについて教えてください。
日本から戻った頃、日本のJWSTechnicaという電解水技術の会社が大学に技術紹介に来ていて、化学製品より環境にやさしい、農業から家畜、そして病院での殺菌能力など幅広い分野でイノベーション起こすメリットがあることに驚いて、ぜひモンゴル科技大で研究開発を進め、ベンチャーを起こしたいと思いました。研究開発が始まり、ウランバートル市が抱えているスモッグや水処理所の消臭にも効果があることを証明しました。
中国から沢山輸入されている環境を汚す化学物質を出来るだけ減らし、製品として安く出来ることが特徴です。
――現在の研究活動を教えてください。
もともと東工大でレーザー加工とレーザー還元の研究を行っていました。特にマグネシウム金属のエネルギーを蓄える材料として太陽から発するレーザー光で還元し、そのどこにでも豊かにあるところを生かし、リサイクル出来ることに注目していました。来年からADB支援で設立予定のレーザー研究センターでこの研究を続ける予定です。
そしてレーザー光で推進出来る無人飛行機の研究も東工大でやっていましたので今、長岡技科大と共同で無人飛行機の研究開発を行っています。モンゴルは広いけど、運送インフラがまだ出来てないところが多いし、草原の家事やゾド雪害で悩む遊牧民に役に立てるということで、共同研究のタイトルを「SkyInfra」と名付けています。高度が5kmまでの無人飛行機だけではありません、地上から10~50kmに存在する成層圏まで上げる風船、そしてそれにつけてリモートセンシング装置の開発研究にも広げています。
――再生可能エネルギーの開発は今が一番旬かと思いますが、それについてどう思いますか?
幸いモンゴルは再生可能エネルギー資源が豊かな国です。しかし不安定なため、このエネルギーをどれだけ安く、どこでも使えるように蓄積できるかが問題です。最近、トヨタのハイブリッド車が増え、それのリチウムやニッケル電池を遊牧生活に利用できるかも大事です。自動車リサイクルを行っているMoARAメンバーのIMAI‐AMKA社をはじめいくつかの企業がその電池を買い取って集めていますが、残念なことはそれに関して正しくない説がテレビで報道されているようでく。研究者として科学に基づく説明が重要ですので、日本側の研究者たちの活躍を期待しています。
モンゴルの資源を利用して将来性が高い電池技術を第一産業として発展させるのが一番です。日本はこの分野では最先端の国ですし、これからの研究開発や新しい産業を起こすにも最大のパートナーだと思います。
――研究一筋で生きることとは?
研究者は国の宝です。資源が豊富だけど労働者が少ないモンゴルにとって、知識経済の発展は重要です。最近の研究調査で分かっているのは温暖化によって砂漠化が猛スピードで広がっている。遊牧民族の生活にも影響して行くとわが国の文化、経済にも被害が及ぶ。モンゴルだけではなく中国とロシアにも良いことはないでしょう。モンゴル人口の7割が35歳までの若者です。昔から若い内に勉強に励むようにと教わってきた国民です。大学希望者数も人口の割合で言うと少なくありません。ソ連教育の良いところを生かして若い研究者を育てていくためには、大学や研究機関の役割りが大きいです。イノベーションのエコシステムが出来ていくうちに、研究者や起業家の良い役割分担が出来て、今よりももっと研究一筋で生きる人たちが増えるでしょう。
――いろいろ教えていただき、ありがとうございました。今後のご活躍を期待しております。
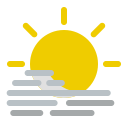 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar